小学生の頃、地元の小劇場で『裸の王様』一人芝居の練習を初めて体験しました。衣装も小道具も手作り、舞台裏の緊張感と、観客と直に交流できる一体感。
そのすべてが、私にとってかけがえのない財産になりました。
この物語を何度も一人芝居で上演してきた中で、王様の“滑稽さ”や“純粋な子どもの目”以上に、自分自身や社会と向き合う勇気こそが最も深いテーマだと感じたエピソードを紹介します。
一人芝居の魅力 自由と挑戦の舞台
何よりも役者自身の表現力と想像力が際立つ点にあります。一人で多役を演じることで、観客に物語の世界を届ける挑戦をし、語り手としての個性が強く反映されます。
魅力のポイント
一人芝居最大の魅力は「逃げ場のなさ」にこそあると私は思います。本番直前、楽屋で他の誰の助けも借りられず、ただ一人で舞台へ飛び込む時の心の震え。
最初は恐怖でしたが、演じる度に“登場人物が自分の中に宿る瞬間”に立ち会えたことで、演劇の奥深さと演者としての成長を直に感じました。
舞台や映画に活躍してきた俳優さんが、俳優人生のしめくくりとして一人芝居をされる方をたくさん知っています。
私自身、ミュージカル舞台に脚本家、演出家、俳優として長い間、やってきましたが一人芝居に辿り着きました。この経験がお役に立てればと思います。
完全な集中力 一人芝居では、舞台上の全てが役者に委ねられます。だから観客は役者が見ている世界と同じものをみるので没頭しやすくなります。
役の多様性を一人で体現 声のトーンや身振り手振りを使い分けることで、一人の役者が多様なキャラクターを見事に演じ分けることができます。
帽子が小道具の代わりになりますよ。詐欺師は、帽子を脱いで恭しく持つ。家来は、ひさしに手をかけてありもしない布を見る。
観客との親密な距離感 一人芝居はシンプルな構成が多いため、観客との心理的距離が近くなり、物語への没入感を深めます。
創造性の極み 限られた要素で物語を紡ぐため、役者や演出家の創造性が存分に発揮され、独自の演出を楽しむことができます。
三つの目で見る 役者の目、観客の目、天の目、この三つの観点で芝居をする。
キャラクター分析と演じ方
はじめに登場人物のキャラクターを分析する。次にキャラクターの特徴を捉えた演じ方をする。この二つを心得ておきましょう。
注意点:ここまでやってもいいのかな、と思うくらいに演じてください。不安なときは、演出家がいる場合には演出家の意見、感想を聞いてみましょう。
一人で練習する場合にはスマホでビデオ撮りしておいて見直すといいですね。観客の目にどう映っているのかがよくわかります。
王様:見栄っ張り、オーバーアクション
王様役を自分で演じてみて驚いたのは、派手な動きや大きな声よりも、「一瞬だけ見せる不安な表情」や、「誰にも打ち明けられない内面の弱さ」が、観客の記憶に残ったことです。
練習では友人に録画を頼んで動きや表情を改良しました。自分なりに失敗を重ねたことで気づいた役作りのヒントも分かち合います。

1日に何度も服を着替える王様。超ナルシスト!
特徴: 自信過剰で虚栄心が強いが、内心は不安を抱えている。
演じ方: 偉そうに胸を張ってどすどす歩く。大げさに腕を振り回す。時折、不安そうな表情を混ぜる。
声は、野太い声が似合う。上ずった甲高い声の表現もおもしろい。ふつうじゃない感じが似合う。
詐欺師たち:薄っぺらい態度、甲高い声
特徴: ずる賢い男達。言葉巧みに王様の虚栄心をくすぐる。相手を操るのが得意なオレオレ詐欺師の真似をすれば特徴が出せる。
演じ方: ヘラヘラとした話し方。声は高めで軽い感じが似合う。いつも小腰をかがめて王様を上目遣いで見やる。おべっか使いの典型。
家来達:王様に媚びているが小心者
特徴: 王に媚びへつらうが、本音を隠し続ける自己防衛的な性格。
演じ方: いつもびくびくしている。揉み手、うつろな目つき、ちょこちょこ歩き、ため息、空威張り。
子ども 無邪気、純真
特徴:無邪気、純真の象徴。真実を語る存在。
演じ方: 明るい濁りのない声で語る。背筋をピンと伸ばし、無邪気にまっすぐな目線がふさわしい。
台本の構成 語りとセリフで構成 1〜7
台本は毎回、自分で全シーンを描写し直してきました。「王様の部屋」に入る瞬間や、子どもが真実を叫ぶ場面では、照明やBGMを自作して雰囲気を作る工夫もしました。
印象に残ったのは、リハーサルで思い切って「観客席に背を向ける演出」を試した時、逆に静まり返った客席の空気から王様の孤独を強く感じたこと。
こうした独自演出例も紹介したいと思います。
セリフの中に語りを入れていくと場面や時期が変わる場合にとてもうまくいきます。
「ここは王様の部屋です」と語れば王様の部屋の場になり、街には人々が待っていました、と語れば街の通りになるのです。
とても便利な使い方なので使ってみてください。日本の伝統的な語りスタイルです。
シーン1: 出だしの文で皇帝のキャラクターをはっきりと出す。昔々、あるところにひとりの皇帝がいました。皇帝は新しいきれいな服がなによりも好きでした。
一時間おきにきれいな服に着替えるのです。よその国なら皇帝は会議に出ていらっしゃいます、というところを「皇帝は衣装部屋にいらっしゃいます」と言いました。
シーン2:二人の詐欺師がやってきて皇帝に言う。「自分の役目にふさわしくない者とバカには見えない布を織る」皇帝はまんまと詐欺師にひっかかり、大金を詐欺師達に与える。
「世界一素晴らしい皇帝陛下に申し上げます。私共は誰も見たことのない聞いたこともない不思議な織物を織れるのでございます」
「ほうほう、どんな織物じゃ」「自分の役目にふさわしくない者とばかには見えないのでございます」
「ほう、これは良い。利口者とばか者もわかるというわけじゃ。早速、作らせよう!」台詞と語りをうまく配置して物語をすすめる。

シーン3:正直者の大臣に布の出来具合を見に行かせる。家臣たちは布が見えないのにショックを受けるが、「素晴らしい布だ!皇帝陛下に申し上げよう」と大嘘を言う。

詐欺師 悪い顔しています!これを演じてね!」

「素晴らしい布でございます!」「ぬぬ、わしには見えない。わしはバカだというのか・・・?」
シーン4: 詐欺師達は大鏡の前で皇帝に服を脱がせ、素晴らしい服を着せる振りをする。
皇帝は服が見えないことの衝撃を受けるが、誰にも気づかれない振りをして腰をねじってみたりにっこり笑ってみたり。大鏡の前でパンツ一丁になる。
シーン5:皇帝の一行は人々に新しい服を見せるパレードをする。誰の目にも皇帝は服を着ていない、裸だと映るが誰も口に出せない。
この様子を描きだす。
大勢の人が皇帝の服を見ようと集まっていました。
「皇帝陛下はバカにな見えないという服をお召しになっている。マントもズボンもすばらしい!人々は口々にもてはやしました」
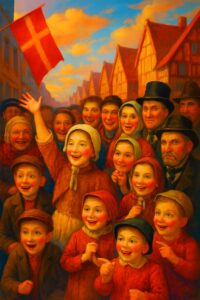
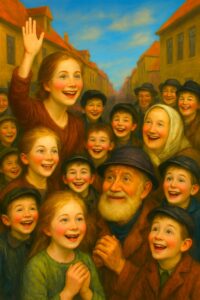
シーン6:男の子が気づく。「何も着ていないよ。王様ははだかだ。パンツ一丁だけだよ」
「王様は何も着ていらっしゃらないって?どう見ても裸だ」裸だ、裸だという声がさざなみのように伝わりました。


「王様は、はだかだ!」
シーン7:王様の内面的な気づきを表現する。「皇帝は困ってしまいました。街のみんなが言うことが本当のような気がしたからです。でも、行列を途中で止めるわけにはいきません。
ますます頭をあげ胸を張って城に帰って行きました。家来達もありもしない裳裾をささげて城へ帰っていきました」

「もしかして裸?は、恥ずかしい・・・」

「やはり、裸?」「王様、すごすご帰って行ったね」
演じ方のポイント 小道具 衣装 シンプルがベスト
- 役の切り替え方法:
小道具は、舞台に用意した椅子一脚と、古着で作ったマントだけ。衣装の大げさな変更よりも、“帽子を深く被る”“マントを肩にかける瞬間”といった細かい変化で、場面転換を分かりやすくしています。
-
自分の経験上、観客との距離がグッと縮まるのは、そうしたささやかな動きや間(ま)を大切にしたときでした。
-
例: 王様は背筋を伸ばし、そっくりかえって歩く。家来達は縮こまった姿勢で揉み手。王様と詐欺師の会話の場合。
-
例えば右側に詐欺師、左側に王様いるという具合に決めておいて、王様が詐欺師に話すときには右に向き、詐欺師が王様に話すときには左に向いてセリフを言う。
-
向きを変えると同時に声も姿勢も変えます。はじめのうちは混乱しますが、慣れれば大丈夫です。
-
何度でも繰り返して練習して体に覚えさせるのがコツです。
- 場面転換には一人で持てる椅子など:簡単な小道具(王冠やマント)でキャラクターを示すと観客に伝わりやすいですが、役の度に王冠をかぶったりマントを羽織ったりするのは簡単ではありません。
- 小道具の持ち替えに気持ちが取られてしまうと演技に集中できないし、観客の気持ちも切れてしまいます。
- 身につける小道具を使うより軽い椅子などを象徴的に置くことをおすすめします。
- 衣装:語り手、王様、詐欺師、街の人、子どもの役などを演じるので特定のキャラクターに偏るのは避けたいですね。
- それで19世紀のイギリス男性の服。茶色のシャツと吊りズボン、茶色のハンチング帽子にしておくと、いrぴろな役を演じることができます。
- 王様は、吊りに両手をかけて太っちょの様子を表現するなど、ちょっと工夫すればいろいろな表現ができますので、発見してみてください。おもしろいですよ。
- 観客との対話を意識する:一人芝居は、観客の反応を感じながら演じることで、一体感を生むことができます。
- 対話のセリフがなくても、観客に問い掛けたいというシーンで目線を客席に飛ばす、台詞とセリフの間に少し間(ま)を取るのも効果的です。
- 落語や講談など日本の伝統話芸が素晴らしい芸を持っていますから参考にされるといいと思います。
- ひとりよがりにならないこと:一人芝居を演じる中で、観客との真のつながりを忘れてしまう瞬間がありました。
- 自分に酔いしれ、表現の心地よさに浸っていたその時、観客が静かに見守っているだけだと思い込んでいました。
- しかし、実際は彼らの心に響くものを届けられていなかったのです。その経験を思い出すたび、私の中に恥ずかしさが湧き上がる一方で、学びの光が差し込みます。
- 失敗を重ねることで、舞台に立つ意味や観客との共感の大切さを深く感じるようになりました。
- 今では、その一瞬一瞬が私を成長させ、新たな挑戦へと導いてくれています。



コメント