「物語から次の一歩へ――」 長年の保育経験を通して痛感するのは、絵本はただ“読む”ものではなく、子どもが“感じて動く”時間を生み出す土壌だということ。「北風と太陽」の話は、子どもたちが自分の考えや感情を自由に表現できる最良の素材です。この記事では、現場で培った独自の導入ステップと、参加型で伸びる台本構成を詳細にお伝えします。
絵本読み語りは、表現力の芽を育てる時間
保育の現場で実践してきたのは、単なる朗読ではありません。「今日の北風はどんな気持ちかな?」と問いかけ、子どもの感情の動きを引き出すダイアログ形式の読み聞かせです。声の強弱や、場面ごとの沈黙も重視し、子どもの“感じる力”を育ててきました。
たとえば『北風と太陽』を読むとき、北風のひゅうっと吹く声には思わず肩をすくめ、太陽のやさしい声にはほっと笑顔がこぼれます。 この「感情を体で受け止める体験」こそが、劇あそびへの第一歩なのです。
絵本選びのポイント
劇あそびの主役となる絵本は、色彩・言葉・登場人物の内面描写が豊かなものが最適です。例えば「北風と太陽」は、意外なほど奥行きのある心理描写や、子どもが想像力を膨らませやすい版画調のイラストなど、現場で本当に“使える”絵本といえます。
保育者が選ぶ際は、実際に子どもが反応したエピソードを記録しておくと失敗がありません。
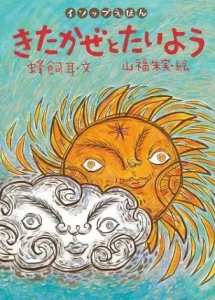
蜂飼耳/絵:山福朱実/出版社:岩崎書店
- 対象年齢:3歳〜小学校低学年
- 特徴:版画調の力強い絵と、詩的でありながら口語的な語りが魅力。
- 教科書掲載実績あり。劇あそびにも使いやすい構成です
『北風と太陽』の深読み|本当の強さとは?
「強いってどういうこと?」 登場人物の行動や心情から、子どもたちは“力”だけではなく、“思いやり”“気遣い”も強さの一部だと気づき始めます。毎回違う反応が出るのが面白い点で、自由な意見交換の場を設けることで、より深い学びへとつながります。経験上、話し合いに“正解”はありません。
北風は、力で旅人のコートを吹き飛ばそうとします。 でも旅人は、寒さに耐えるために、コートをもっとしっかりと身につけてしまう。 一方、太陽は、旅人の気持ちを変えようとはしません。 ただ、あたたかく照らし続けることで、旅人が自分の意思でコートを脱ぐのを待ちます。
この違いは、子どもたちにもはっきり伝わります。 「北風は怒ってる」「太陽はやさしい」――その感覚の中に、“本当の強さ”とは何かを感じ取る力が育っていくのです。
ワンポイントアドバイス劇あそびの前に、「北風と太陽、どっちが“つよい”と思う?」と聞いてみましょう。 「北風に決まってるよ」と答える子どもたちが多いのですが、隣同士で話し合っているうちに「強くても意地悪は良くないよね」「でもさ、強い方が勝つよね」と話が白熱してきます。子どもってすごいなあ、と思う場面に何度も出会います。
劇あそびへの導入|読み語りから自然につなげるコツ
読み終わった直後の“やってみたい!”の声が出たら、即座にアクションにつなげましょう。導入時には、「もし自分が北風だったら?」などの質問に加え、身体をつかって“北風”や“太陽”っぽい動き・表情を実演し、参加のハードルを下げます。さらに、少人数でのロールプレイや即興コーナーもおすすめです。
この“自分からやりたい”という動機を大切にしながら、読み聞かせから劇あそびへとつなげていくのが大人の役目です。 次に紹介する問いかけを使うと、自然と子どもたちの気持ちが動きます。
子どもたちの「やってみたい!」を引き出す問いかけ
読み語りのあとに、こんな問いかけをしてみましょう:
- 「北風ってどんなふうに吹いてた?」
- 「太陽はどんな気持ちだったと思う?」
- 「旅人は、どうしてコートを脱がなかったのかな?」
- 「もし自分が旅人だったら、どうする?」
- 「北風と太陽、どっちが勝ったのかな?」
- 「太陽が勝った理由は何だと思う?」
こうした問いかけは、子どもたちの内側にある“感じたこと”を引き出すきっかけになります。 そして、「やってみたい!」という気持ちが自然に生まれたとき、劇あそびの準備はもう整っています。
ワンポイントアドバイス 「どっちが強いと思う?」という問いは、子どもたちの価値観を引き出す魔法の言葉。 答えに正解はありません。感じたことをそのまま受け止めましょう。
役の分け方とアレンジ方法
配役は「やりたい」「なりきりたい」役を優先し、風の精・光の精・雲などのサブキャラクターを追加することで参加枠を広げます。子どもがアイデアを出した場合、それを即興で役に反映させてみるのもユニーク。配役の選び方自体を1つの活動にして、希望が重なれば抽選や交代制に。短時間の体験コーナーを設けることで、見学だけの子も途中参加できる流れを作れます。
たとえば風の精、光の精、雲などを加えると、クラス全員が関われる劇になります。 動くのが好きな子には風の精、静かに演技したい子には旅人、明るい性格の子には太陽など、その子にぴったりの役を一緒に考える時間も大切です。
配役を「得意・不得意」で分けるより、「やってみたい!」という気持ちを尊重することが成功の鍵です。
ワンポイントアドバイス 配役は“できること”ではなく、“やってみたい気持ち”を大切に。 自分で選んだ役は、責任感と表現力を自然に引き出します。
幼児向け完全通し台本『北風と太陽』
対象年齢:5〜6歳/演目時間:約10〜12分/人数:5人〜全員参加型対応
登場人物
- ナレーター
- 北風
- 太陽
- 旅人
- 空の声
- 光の精・風の精(人数に応じて追加可能)
第1幕:みんなで空の様子・天気を表現(雲の精・鳥・森などを自由に追加可能)
(舞台中央に北風と太陽。空の声は上手、ナレーターは下手に立つ)
ナレーター ここは空の上。風がふいて、光がさすところ。 北風と太陽が出会いました。
(北風、胸を張って登場。太陽は静かに微笑みながら現れる)
北風 おい、太陽!おまえはいつもぬるい顔して照らしてるけど、 ほんとうに強いのは、ぼくの風だ!
太陽 強さって、なんだろう? ぼくは、あたためるのが好きなんだ。
北風 あたためる?そんなの弱いやつのやり方だよ。 ぼくは、吹けばなんだって動かせる。 それが、ほんとうの力だ!
太陽 動かすことと、届くことはちがうよ。 ぼくは、心に届く光を信じてる。
空の声 ふたりは、どちらが強いか、くらべることにしました。 ちょうど、下の道を旅人が歩いています。
(旅人、ゆっくりと舞台下手から登場。コートを着て、うつむきながら歩いている)
北風 よし!あの旅人のコートをぬがせた方が勝ちだ!
太陽 いいよ。ぼくは、ぼくのやり方でやってみる。
第2幕:北風が挑戦する場面では、風の精リーダーの掛け声や旅人側との攻防シーンを増やす
(北風、風の精たちとともに構える。旅人は中央で立ち止まり、コートを抱えている)
ナレーター 北風は、空いっぱいに息をすいこみました。 風の精たちも、力を合わせて吹きはじめます。
北風 いくぞーーーっ!ビューーーーッ!!
風の精たち ビューッ!ビューッ!もっと吹けー!
(旅人、風にあおられながらよろける)
旅人 うわっ…さむっ…! 風が…いたい…! コートがとばされそう…でも…ぬいだら…もっと寒い!
北風 もっとだ!もっと吹け! この風なら、ぜったいにぬぐはずだ!
旅人 やめて…やめてよ… なんでこんなに吹くの? ぼくがなにか悪いことしたの?
旅人 寒い…こわい… でも…ぬげない… ぬいだら、もっとつらくなる気がする…
空の声 北風が吹けば吹くほど、旅人はコートをぎゅっとだきしめました。 力では、心は動きませんでした。
第3幕:太陽の挑戦は、光の精が暖かさや安心感を全員で表現し、太陽と旅人が互いに心の声・ナレーションでやり取り
(太陽、静かに照らし続ける。光の精たちがゆっくり舞う。旅人はうずくまったまま)
太陽 ぼくは、ここにいるよ。 ずっと、照らしてる。
(旅人、少しずつ体を起こす。顔を上げて太陽を見る)
旅人 …なんで、光をくれるの?
太陽 ぼくは、光だから。
旅人 さっきは、こわかった。 風がつよくて、いたかった。 でも…今は、あったかい。
太陽 うん。
旅人 あなたは、なにも言わないのに、あったかい。 ぼくの中が、ぽかぽかしてる。
太陽 それなら、よかった。
旅人 まだ、ぬげないけど… あるいてみたい。 この光のなかを。
第4幕:川遊びシーンは全員参加型。「うまれかわった気持ち」をその場で一言ずつ言う時間を作る
(旅人、太陽の光に包まれながら、舞台下手にある川の前に立つ)
旅人 このコート、ずっと着てた。 寒いときも、こわいときも。 でも…もう、いらないかも!
(旅人、コートを脱ぎ、ポンと地面に置く)
旅人 わーっ!水だ!川だ!
(旅人、川に飛び込むように走る)
旅人 つめたい!でも、きもちいいーっ! ぴちゃぴちゃ!ぴちゃぴちゃ! ぼく、うまれかわったみたい!
旅人 もう寒くない! もうこわくない! ぼく、あるくよ!ジャンプしてもいい?
太陽 もちろん。 あなたの歩きたいように、歩いていいんだよ。
旅人(ぴょんと跳ねながら) 太陽さん! いっしょに歩こう! ぼくはもう、こわくない!
第5幕:気づきの時間では、観客(保護者・友達)も一緒に“自分だったら?”を考えるミニワークあり
(北風、舞台奥から静かに出てくる)
北風 ぼくは、風で動かそうとした。 でも、旅人は動かなかった。 太陽は、なにも言わずに照らしただけ。 それで…旅人は、自分で動いた。
北風 …勝ったのは、おまえだ。 強さって、力じゃなかったんだな。
太陽 ぼくは、ただ照らしただけ。 なにかをさせようとは思わなかった。 でも、光が届いたなら―― それは、心が動いたから。 それが、ほんとうの強さだと思う。
空の声 こうして、勝負は決まりました。 勝ったのは、太陽。 でも、ほんとうに強かったのは―― 自分で決めて歩き出した、旅人かもしれません。
ナレーター 北風は、風を吹き続けます。 太陽は、光を照らし続けます。 そして旅人は―― 自分の足で、歩き続けます。
全員(力強く) おしまい。
セリフ・シーン案は分量を増やし、子ども自身の言葉を活かした即興コーナーも追加
劇の練習をしていると、台本通りに進まないことはよくあります。 むしろ、それが“普通”だと言ってもいいくらいです。
子どもたちは、演じながら気づき、感じ、思いつきます。 セリフが変わったり、シーンが増えたり――それは、心が動いている証です。
だからこそ、台本は「守るもの」ではなく「育てるもの」。 どんどん変えていい。どんどん足していい。 その過程で、子どもたちのやる気や表現が、自然と引き出されていきます。
台本通りに進めなければならない、と思わなくていいのです。 大切なのは、子どもたちが“自分のことば”で物語を生きること。 その瞬間こそが、劇あそびの本当の価値です。
劇あそびを成功させる5つのポイント
劇あそびは、子どもの心がそのまま表れる特別な時間です。 先生が完璧な台本を準備しても、“その子らしさ”が生かされなければ意味がありません。 大切なのは、「子ども一人ひとりの気持ちが動く体験」にすることです。 私が多くの園で実践してきた中で成果が出た5つのコツを紹介します。
① 配役を決める「みんなで話し合う場」が効果的
配役は先生が決める――それが“ふつう”と思われがちですが、 実は、子どもたち自身が「やってみたい」「挑戦してみたい」と思える役を選び、演じる方が、ずっと効果的です。
みんなで話し合う場をつくると、意外なほどすんなり決まることも多く、 その中で子どもたちは、自分の気持ちを伝えたり、友だちの考えを受け止めたりする経験を重ねていきます。
そして何より驚かされるのは―― 自分で選んだ役を演じたときの、子どもたちの表現の深さです。 「えっ、こんなにうまいの⁉」と、思わず感動してしまうことが何度もあります。
自分で選んだ役を、自分のことばで演じる。 そのプロセスこそが、劇づくりの大切な土台であり、 「みんなで話し合う場」のいちばんのねらいです。
② セリフ覚えは“楽しく”が基本!セリフカードを使った“言葉+絵”で覚える方法
セリフカード・日替わりコーナー・アドリブタイムで、子どもの表現力がぐんぐん伸びる
劇あそびや発表会で、子どもにセリフを覚えさせる場面―― 先生が「ちゃんと覚えてね」と言えば言うほど、子どもは緊張してしまいます。 でも、セリフ覚えは“楽しく”が基本。その方が、子どもたちはずっとイキイキと表現できるのです。
■セリフカードで“言葉+絵”の記憶をサポート
セリフを覚えるときは、場面の絵とセリフをセットにしたカードを作ってあげると効果的です。 絵を見ながら言葉を思い出すことで、記憶の負担が減り、自然にセリフが身につきます。 何より、子どもたちが「この場面、好き!」と感じながら覚えられるのが大きなポイントです。
■日替わりセリフコーナーで“遊びながら”定着
保育室や教室の一角に「今日のセリフコーナー」を設けて、 毎日ひとつずつセリフを紹介するのもおすすめです。 「今日のセリフ、言えるかな?」と声をかけるだけで、子どもたちは自然と口に出して練習します。 遊び感覚で取り組めるので、緊張感なく、楽しく覚えられます。
■アドリブタイムで“自分のことば”を引き出す
さらに、練習の中に“アドリブタイム”を設けてみましょう。 「この場面、自由に言ってみていいよ」と伝えるだけで、子どもたちは驚くほど豊かな表現を見せてくれます。 実際、先生が書いたセリフよりも、子ども自身のアドリブの方が真に迫っていることも少なくありません。
子どもたちは、自分のことばで語るとき、目が輝きます。 その瞬間こそが、劇あそびの本当の価値です。
③ 緊張への対応:「見ているだけ参加」「BGM係」「応援係」などの裏方体験で、劇あそびがもっと楽しくなる
劇あそびや発表会の練習で、セリフや動きに緊張してしまう子、いますよね。 「やりたい気持ちはあるけど、前に出るのはちょっと…」という子にこそ、裏方体験の導入が効果的です。
■「見ているだけ参加」で安心感を
まずは、“見ているだけ”の参加を認めること。 「今日は見てるだけでいいよ」「好きな場面だけ出てみようか」と声をかけるだけで、 子どもは安心して劇の世界に関わることができます。
見ているうちに、「あの役、やってみたいかも」と気持ちが動くこともよくあります。 無理に引っ張らず、待つことも大切な支援です。
■「BGM係」で物語の空気をつくる
劇の場面に合わせて、楽器や音楽を担当する“BGM係”を設けるのもおすすめです。 タンバリン・鈴・カスタネットなど、簡単な楽器を使って、場面の雰囲気を盛り上げます。
「この場面は静かに」「ここは元気に!」と、音で物語を支える体験は、 子どもたちに“自分も劇の一部”という実感を与えてくれます。
■「応援係」で仲間を支える喜びを
劇の練習中、「応援係」として、仲間に拍手を送ったり、声をかけたりする役割も効果的です。 「○○ちゃん、すごかったね!」「もう一回やってみよう!」と声をかけることで、 人を応援する喜びと、仲間とのつながりが育まれます。
応援係を経験した子が、「次は自分もやってみたい」と前に出てくることもあります。
劇の練習をしていると、台本通りに進まないことはよくあります。 むしろ、それが“普通”だと言ってもいいくらいです。
子どもたちは、演じながら気づき、感じ、思いつきます。 セリフが変わったり、シーンが増えたり――それは、心が動いている証です。
だからこそ、台本は「守るもの」ではなく「育てるもの」。 どんどん変えていい。どんどん足していい。 その過程で、子どもたちのやる気や表現が、自然と引き出されていきます。
台本通りに進めなければならない、と思わなくていいのです。 大切なのは、子どもたちが“自分のことば”で物語を生きること。 その瞬間こそが、劇あそびの本当の価値です。
衣装作りは自分で考えて作るのが楽しい!
家庭にも広がる表現力と誇り――素材選びから子どもの心が動き出す
劇あそびで子どもが自分の衣装をつくると、 その役になりきる力がぐんと高まります。 そしてその変化は、保育室だけでなく、家庭の中でもはっきりと現れます。
「風の役だから、今日は風の声で話すね」 「この帽子、ぼくが作ったんだよ。風がビューって吹くときにかぶるの」 「ママ、光の役ってね、こうやって歩くんだよ」
そんなふうに、家庭でも劇の世界を生きるようになるのです。 保護者からは、こんな声が聞こえてきます。
「あんなに恥ずかしがり屋だったのに、家では堂々と演じていてびっくりしました」 「自分で作った衣装を毎日見せてくれて、誇らしそうでした」 「劇あそびが、こんなに家庭に広がるとは思いませんでした」
■身近な素材で、十分に雰囲気は出せる
衣装づくりに特別な材料は必要ありません。 家庭にあるもの・押し入れに眠っているもの・100円ショップの素材で、十分に雰囲気が出ます。
- コートの役:おうちのシャツや古布を巻くだけ
- 光の役:黄色いスカーフ、紙テープ、キラキラ包装紙など
- 風の役:青いリボン、ビニールひも、レジ袋をふわっと揺らす
さらに、古着・鍋の蓋・空き箱・帽子・スカーフ・カーテンの切れ端など、 「これ、使えるかも?」と目を向けるだけで、素材の見え方が変わってきます。
子どもたちは、「これがぼくのコート!」「わたしの光!」と、 自分の役に誇りを持ち、衣装を大切に扱うようになります。
■衣装づくりは、表現の一部
衣装は、ただの飾りではありません。 子どもが自分の役を理解し、愛着を持つための“表現の一部”です。 自分でつくったものには、自然と気持ちがこもります。
劇あそびひとつで、 創造力・自己肯定感・家庭とのつながり――すべてが育っていくのです。
衣装づくりから家庭に物語が広がる
衣装づくりを通して、子どもは役に誇りを持ち、 劇の世界を家庭でも生きるようになります。 素材は、家庭にある“ちょっとしたもの”で十分。 大切なのは、子ども自身がつくること・感じること・誇りを持つことです。
劇あそびが家庭にも広がる、子どもの“なりきり力”に保護者もびっくり!
劇あそびで自分の衣装をつくった子どもは、 その役になりきる力がぐんと高まります。 そしてその変化は、家庭の中でもはっきりと現れます。
「風の役だから、今日は風の声で話すね」 「この帽子、ぼくが作ったんだよ。風がビューって吹くときにかぶるの」 「ママ、光の役ってね、こうやって歩くんだよ」
そんなふうに、家庭でも劇の世界を生きるようになるのです。
保護者の方からは、こんな声が聞こえてきます。
「あんなに恥ずかしがり屋だったのに、家では堂々と演じていてびっくりしました」 「自分で作った衣装を毎日見せてくれて、誇らしそうでした」 「劇あそびが、こんなに家庭に広がるとは思いませんでした」
一つの衣装で、子どもは変わります。 それは、ただの布や紙ではなく、自分でつくった“自分の物語のしるし”だからです。
劇あそびは、保育室だけで終わりません。 家庭にも、子どもの表現と誇りが広がっていくのです。
- コート:おうちのシャツや布を巻くだけ
- 光:黄色いスカーフや紙テープ
- 風:青いリボンやビニールひもをふわっと
「これがぼくのコート!」「わたしの光!」と、自分の役に誇りを持てるようになります。 衣装づくりも、表現の一部として楽しんでほしい時間です。
ふりかえり活動|心に残ったことを言葉にする
劇あそびは、子どもが“感じる”時間です。 演じることで心が動き、その余韻が残っているうちに、ふりかえりの時間をつくることがとても大切です。
私は現場でいつも、劇のあとに10分だけでも「感じたことを話す時間」を意識して設けています。 言葉でも、絵でも、沈黙でもかまいません。 「こわかった」「うれしかった」「光になれてよかった」――そんな一言が出てくるだけで、劇あそびが“自分のもの”になります。
このふりかえりの時間があるかないかで、次の表現へのつながり方がまったく違ってきます。 だからこそ、ほんの少しでもいい。心に残ったものを、外に出す時間を、ぜひ意識してみてください。
よくある質問(Q&A)
劇あそびを実践していると、保育者・親・地域スタッフの方からいろいろな質問をいただきます。 ここでは、現場でよく聞かれることに、私自身の経験をもとにお答えします。
Q. 5歳児でもセリフを覚えられる?
A. はい、覚えられます。ただし「覚える」よりも「感じて話す」ことを大切にしています。 セリフを動きとセットにしたり、絵や色で台詞カードを工夫すると、自然に口から出てくるようになります。 「セリフ=気持ちの言葉」として扱うと、子どもたちは驚くほど表現してくれます。
Q. 参加したくない子にはどう対応すれば?
A. 役以外の“サポート係”や一言セリフだけ担当など、無理せず関われる形を増やす。小道具を出し入れする係、効果音を担当する係、客席にいて応援する係も立派な劇あそび参加です。セリフがなく動く、 「光の精で動くだけでもいいよ」「見守る役もあるよ」と伝えると、安心して関われます。
見ているうちに「やってみたい」が芽生えることも多く、そのときに交代できるようにしておくと自然な参加が生まれます。
Q. 保護者への説明はどうすれば?
A・事前に「この劇は、子どもが自分で考えて動く力を育てるものです」とお伝えすると、 保護者の方のまなざしがぐっと温かくなり、 子どもたちも安心して、自分らしく舞台に立つことができます。
保護者の皆さまへ
今回の劇あそびは、子どもたちが自分で考え、動き、感じることを何より大切にしています。 セリフを覚えることや、演技の完成度を目指すのではなく、 「やってみたい」「伝えたい」「仲間と一緒にやりたい」――そんな気持ちが育つことを目的としています。
劇の中で、セリフが飛んでしまったり、動きが止まってしまう場面もあるかもしれません。 でも、それも含めてその子の“今”の表現です。 その瞬間にこそ、子どもたちの心が動いているのです。
どうか、「うまく演じること」よりも、 その子の心がどんなふうに動いたか、どんな表情で仲間と関わっていたか―― そんなところに目を向けていただけたら嬉しいです。
劇あそびは、子どもたちの成長の通過点です。 その一歩一歩を、どうぞ温かく見守ってください。
Q. アドリブやセリフの変更はOK?
A・子どもが“自分の言葉”で語りたくなったら、それは成長の証です
劇あそびの中で、子どもが「このセリフ、ちょっと変えたい」「こう言った方がいいと思う」と言い出すことがあります。 それは、その子が役を理解し、自分の言葉で伝えたいと思っている証拠。 まさに、表現力と主体性が育っている瞬間です。
台本はあくまで“土台”です。 その上に、子どもたちの自由な表現が乗ることで、劇は生きたものになります。
私は、アドリブやセリフ変更をむしろ歓迎しています。 変更したい理由を聞き、大筋から外れていなければ、その工夫を褒めて採用しています。 そうすることで、子どもは「自分の考えが認められた」と感じ、やる気と自信がぐんと育ちます。
劇あそびの醍醐味は、その子らしさが出る瞬間にあります。 だからこそ、指導者も「正しく言わせる」ことより、 子どもの表現を受け止め、学び続ける姿勢が求められるのだと思います。
Q. 家庭でも劇あそびに挑戦したい時のコツは?
A. 特別な準備は必要ありません。 劇あそびは、保育室だけのものではなく、家庭の中でも自然に始められる表現活動です。
まずは「ごっこ遊び」からスタート。 「お店屋さん」「風ごっこ」「おばけごっこ」など、日常の延長で“役になりきる”楽しさを味わえます。
衣装や小道具も、家にあるもので十分。 古着・スカーフ・空き箱・紙テープなど、押し入れや100円ショップで見つかる素材が、 子どもにとっては“自分の物語のしるし”になります。
セリフは自由でOK。 子どもが自分の言葉で語り始めたら、それは表現力と自信が育っている証です。 恥ずかしがる子には、応援係・音楽係など、無理なく関われる役割をつくってあげましょう。
劇あそびを通して、家族の会話が増え、笑顔が広がり、心がつながる時間が生まれます。 家庭の中に、小さな舞台をつくってみませんか?
家庭で劇あそびをすることで、子どもたちにはさまざまな力が育ちます。 まず、自分の言葉や動きで伝えようとする表現力が自然に芽生えます。 「こう言ってみたい」「こんなふうに動きたい」と、自分の思いを形にする力が育っていくのです。
また、物語の世界を生きることで、想像力もぐんと広がります。 「風ってどんな声?」「光ってどう動く?」と考える時間が、創造の土台になります。
そして、家族で一緒に演じることで、絆が深まります。 「楽しかったね」「あのセリフ、面白かった!」といったやりとりが、会話と笑顔を増やし、心を近づけてくれます。
さらに、「自分で考えたセリフを言えた!」「みんなが拍手してくれた!」という経験は、自信につながります。 子どもは、自分の表現が受け止められたことで、自己肯定感を育んでいきます。
劇あそびは、家庭の中に“物語の時間”を生み出し、子どもの心と家族の絆を育てる、かけがえのない時間になります。
まとめ|子どもたちの心に届く劇あそび
物語に“動き”が加わった瞬間、子どもたちの表情も驚くほど変わります。劇あそびは、心の奥から湧き出る力を自分で発見する場です。大切なのは、成功や失敗より“自分で考え感じる”経験そのもの。この記事が、保育者や家庭の皆さんの現場で、子どもと物語をもっと深く楽しむ時間のヒントになりますように。
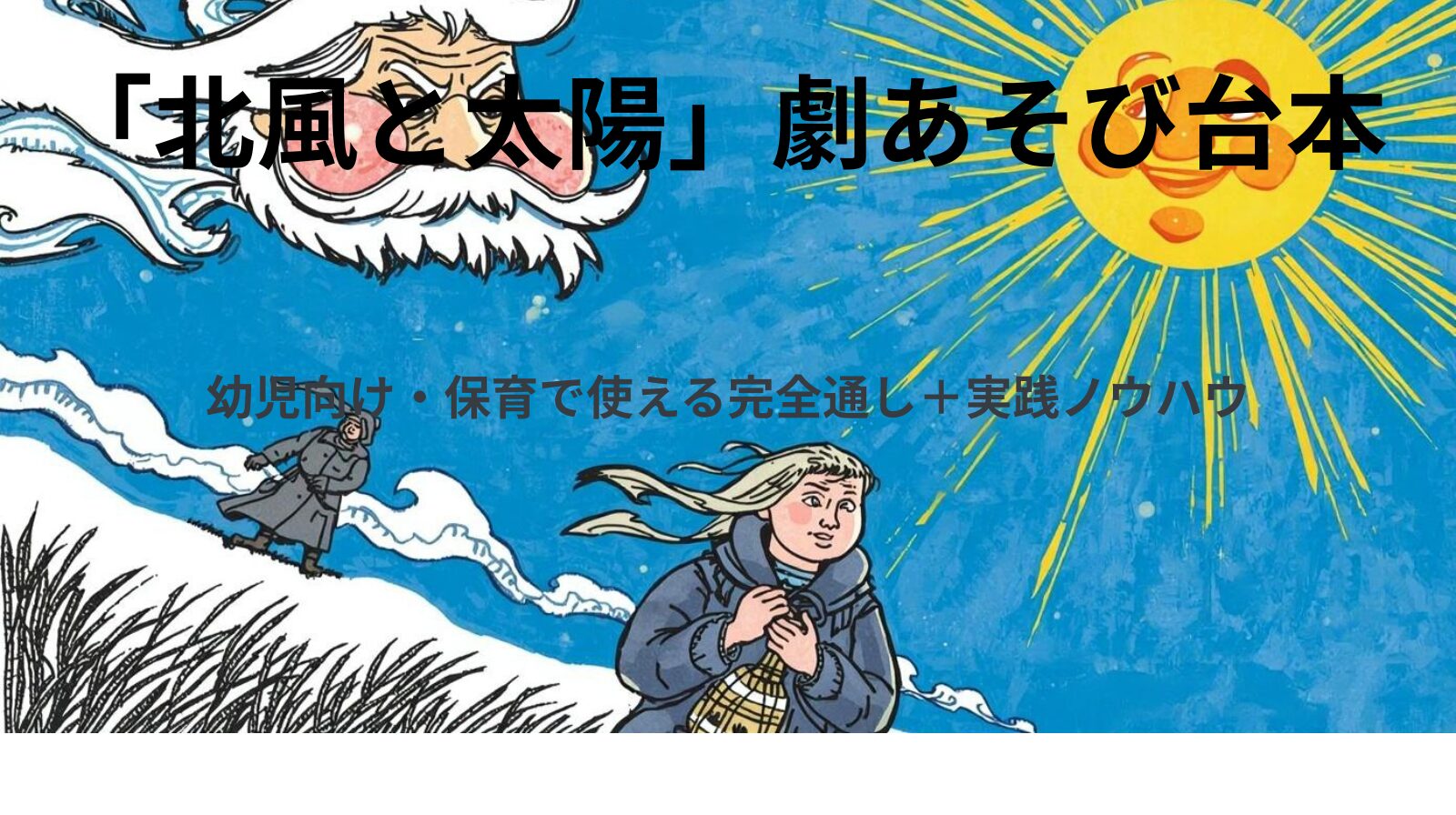


コメント