はじめに|昔話は“心を育てる物語
語りから始まる教育の力
「おむすびころりんって知ってる?」 子どもたちにそう問いかけると、 「穴に落ちるやつ!」「ねずみが出てくる!」と、目を輝かせて答えてくれます。 でも、私が語るのは、“ほんとうの『おむすびころりん』”です。
良いおじいさんと悪いおじいさんの対比。 ねずみたちの餅つき歌。 猫の真似をして宝物を奪おうとする場面。 そして、悪いおじいさんがもぐらになってしまう結末――
この昔話には、正直・感謝・欲深さへの報いなど、 子どもたちの心を揺さぶるテーマがぎゅっと詰まっています。
私は、保育現場・地域・講座などで、何度もこの昔話を語り、劇あそびへとつなげてきました。 子どもたちは、演じながら「どう生きるか」を、自分の言葉で考え始めます。
昔話は、子どもたちの心に“生き方の種”をまくもの。 語りは、その種まきです。
だからこそ、絵本の選び方、語り方、ふりかえりの時間まで、 すべてに愛と責任が必要だと、私は感じています。
このシリーズでは、『おむすびころりん』を題材に、 絵本の読み語りから劇あそびへの流れ、台本、演出、ふりかえり活動までを、 現場の実践に基づいて、わかりやすくご紹介します。
現場一筋の語り手として伝えたいこと
私は、保育現場・地域・講座などで、何度もこの昔話を語り、劇あそびへとつなげてきました。 子どもたちは、演じながら「どう生きるか」を自分の言葉で考え始めます。 語りは、心を育てる“種まき”です。 だからこそ、絵本の選び方、語り方、ふりかえりの時間まで、すべてに愛と責任が必要だと感じています
このシリーズ記事のねらい
このシリーズでは、昔話『おむすびころりん』を題材に、 絵本の読み語りから劇あそびへの流れ、台本、演出、ふりかえり活動までを、実践に基づいてご紹介します。 保育者・絵本講師・親御さんが、すぐに使えて、深く学べる内容を目指しています。
絵本の読み語りから始める劇あそび
語りの力で物語が“自分ごと”になる
昔話は、ただの娯楽ではありません。 語りによって、子どもたちは物語を“自分のこと”として感じ始めます。
語り手の声の表情、間の取り方、登場人物の気持ちを伝える語り口―― それらが、子どもたちの心に届くとき、物語は“生きた体験”になります。
語りの場面では、子どもたちが笑ったり、驚いたり、静かになったりします。 「おむすびが転がった!」「ねずみが歌ってる!」―― その反応こそが、心が動いている証です。
語りのあとに生まれる“問い”が、劇あそびの種になる
語り終えたあと、私は必ずふりかえりの時間をつくります。 「どっちのおじいさんになりたい?」「ねずみはなぜ怒ったの?」―― そんな問いかけに、子どもたちは自分の言葉で答え始めます。
ある子は「猫の真似はこわいと思った」と言い、 ある子は「ねずみがかわいそうだった」と絵に描きました。 この時間が、劇あそびへの“心の橋”になります。
劇あそびは、ただセリフを覚えて演じるものではありません。 物語を感じ、自分の中に取り込む時間があってこそ、演じる意味が生まれるのです。
ふりかえりの時間が心の土台になる
ふりかえりでは、子どもたちの言葉をそのまま受け止めます。 「悪いおじいさんは、ねずみに嫌われたんだね」 「ぼくは、良いおじいさんになりたい」 そんな言葉が出てくるとき、物語は子どもの中で“生きている”のです。
まとめ|語りは、心を育てる“種まき”
昔話を語ることは、子どもたちの心に“生き方の種”をまくことです。 語りのあとに生まれる問い、感じたことを言葉にする時間、そして劇あそびへとつながる流れ―― それらすべてが、子どもたちの人格と感情を育てる土壌になります。
私は、現場一筋で語り続けてきました。 そして今、次の時代に向けて、私が体験して得た知識を皆さんに差し上げたいと思っています。語りは、心を育てます。 誠実な絵本と、誠実な語りがあれば、子どもたちは必ず感じて、考えて、育っていきます。
おすすめ絵本紹介|『おむすびころりん』を語るために
〜絵本選びは“食材選び”。語り手の責任として〜
絵本選びは“食材選び”――語り手の責任
「絵本選びは食材選び」――これは、私が現場でいつも伝えている言葉です。 子どもに渡す絵本は、心の栄養になるものでなければなりません。
昔話は、ただ楽しいだけの物語ではありません。 善悪の対比、感謝と欲望、行動の報いなど、子どもたちの心を育てる要素が詰まっています。 だからこそ、絵本は“かわいいだけ”ではいけません。
最近は、昔話の絵本でも場面が省略されていたり、言葉が軽くなっていたりするものが少なくありません。猫の真似をする場面がない。 もぐらになる結末が描かれていない。 それでは、物語の本質が伝わらないのです。
語り手として、教育者として、私はこう思います。 「絵本は、誠実でなければならない」
一番のおすすめ絵本|偕成社版『おむすびころりん』
私が語りにも劇あそびにも使っているのが、 偕成社版『おむすびころりん』文:よだじゅんいち/絵:わたなべさぶろうです
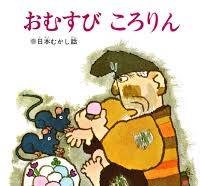
この絵本は、昔話の流れを誠実に、丁寧に描いている点で、他とは一線を画しています。
- 良いおじいさんと悪いおじいさんの対比が明確
- ねずみの餅つき歌がリズムよく描かれている
- 猫の真似をする場面がしっかり描写されている
- もぐらになる結末まで、因果応報の流れが丁寧に描かれている
- 絵の表情が豊かで、語り手の間や声の表情を引き出し読み語りのあとに、子どもたちが「やってみたい!」と自然に言い出す―― そんな力を持った一冊です。 この絵本は、語り手の“相棒”になります
台本のねらいと特徴|育てたい力と物語の軸
〜“演じる”ことは、心を動かす体験〜
劇あそびは“心の体験”になる
劇あそびは、ただセリフを覚えて演じる活動ではありません。 物語を感じ、自分の中に取り込む時間があってこそ、演じる意味が生まれます。
『おむすびころりん』の劇あそびでは、子どもたちは登場人物の気持ちを想像し、 「自分だったらどうする?」と考えながら、心を動かして演じるようになります。ねずみの歌を楽しそうに歌う子 猫の真似をする場面で、ちょっと照れながらも挑戦する子 もぐらになる結末を演じながら、静かに考える子。それぞれの姿に、物語との対話が生まれています。
育てたい力|表現・感情理解・自己決定
この台本には、以下のような育てたい力を込めています:
- 表現力:声・動き・表情で気持ちを伝える力
- 感情理解:登場人物の気持ちを想像し、共感する力
- 自己決定力:「どっちのおじいさんになりたい?」と自分で選ぶ力
- 協働性:役を分け合い、場面をつくる仲間との関わり
- 倫理的思考:欲張るとどうなる?正直に生きるとは?考える台本は、ただの“セリフ集”ではありません。 子どもたちの心を育てる“設計図”です
劇あそび台本|『おむすびころりん』
対象:年長〜小学校2年生/演じる人数:8〜15人程度(調整可) 時間:約10〜15分/語り手あり・歌あり・動きあり
登場人物(調整可能)
- 語り手(先生または子ども)
- 良いおじいさん
- 悪いおじいさん
- ねずみたち(3〜6人程度)
- ねずみの長(リーダー)
- もぐら(ラストのみ)
- 猫(真似される存在として登場)村人(ふりかえり場面に追加)
場面①:山道とおむすび
語り手 山のてっぺん、風がすーっと通る道。 良いおじいさんが、腰をおろして言いました。
良いおじいさん (包みを開けて) 今日もよく働いた。さあて、お昼は…おむすびじゃ。 (転がる動き) あっ!こらこら、待て待て〜!ころころころりん…ああ〜!
語り手 おむすびは、ころころころりん…ぽとん! 穴の中へ、落ちてしまいました。
良いおじいさん (のぞきこみながら) なんだ?この穴…おむすび、どこ行ったんじゃ?
場面②:ねずみのもちつ
語り手 穴の奥から、こんな歌が聞こえてきました。
ねずみたち (リズムよく、動きながら) ぺったん ぺったん ねずみのもちつき! ぺったん ぺったん うたってつこう!
ねずみの長 おむすび、ありがとう!おじいさん、こっちこっち!
良いおじいさん (驚きながら) おお、ねずみのもちつきとは…こりゃ楽しい! わしもついていいかの?
ねずみたち もちろん!ぺったん ぺったん! (全員で餅つきの動き)
ねずみの長 おじいさん、これ、お礼の宝物です!
良いおじいさん (感激して) こんなにたくさん…ありがたいことじゃ! ありがとう、ありがとう!
場面③:悪いおじいさんと猫の真
語り手 その様子を、じーっと見ていたのは――
悪いおじいさん ふん、わしも宝物がほしいわい。 おむすびを持って…ふふふ、猫の真似でもしてやるか!
語り手 穴の前で、悪いおじいさんは――
悪いおじいさん (大げさに) にゃーん!にゃーん!ガオー! (ねずみたちが驚く)
ねずみたち きゃー!猫だ!逃げろー!
ねずみの長 待て!これは猫じゃない!おじいさんの真似だ!
ねずみたち なんてことするの! 追い出せ!追い出せ!
悪いおじいさん ちょ、ちょっと待って!わしは…わしは…
場面④:もぐらになる結末
語り手 悪いおじいさんは、穴から追い出されて、 そのまま、もぐらになってしまいました。
もぐら (静かに) 暗い穴の中で、ひとりぼっち… もう、宝物なんていらない…
場面⑤:ふりかえりの語り
語り手 良いことをすれば、良いことが返ってくる。 欲ばると、思いがけない報いがある。 昔話は、そんなことを、静かに教えてくれます。
村人(追加役) わたしは、良いおじいさんみたいになりたい。 ねずみと仲良くしたい。
子どもたち(自由セリフ) ・猫の真似はこわかった! ・もちつき、楽しかった! ・もぐらになったの、ちょっとかわいそう…
場面⑥:終わりの語りと子どもたちの言葉
〜物語を閉じるのは、子ども自身の心〜
語り手 こうして、良いおじいさんは、ねずみたちと仲良くなり、 悪いおじいさんは、もぐらになって、静かな穴の中で暮らすことになりました。
語り手(少し間をとって) このお話を見て、みんなはどう思ったかな?
(舞台中央に、子どもたちが一人ずつ出てきて、自分の言葉で語る)
子ども① ぼくは、もちつきが楽しそうだった。ねずみと一緒につきたい!
子ども② 猫の真似はこわかった。でも、ちょっと笑っちゃった。
子ども③ 悪いおじいさん、かわいそうだったけど…やっぱり、ねずみをだましたらダメだと思う。
子ども④ わたしは、良いおじいさんみたいに、ありがとうって言える人になりたい。
(全員が並び一礼)
全員 ありがとうございました!
演出メモ|“語り・動き・感情”を引き出す工夫
〜先生も子どもも、一緒に楽しめる劇あそびのヒント〜
劇あそびは、子どもたちのためだけのものではありません。 先生自身が「やってみたい」「楽しそう」と思えることが、子どもたちの心を動かす第一歩になります。
今の保育現場では、時間も人手も足りず、「わかっているけど、できない」と感じている先生も多いと思います。 でも、自分の声で語り、体で動き、仲間と笑い合う体験は、どんな時代でも“心の根っこ”を育てる力があります。
この演出メモは、そんな先生たちに向けて、「これならできそう」「ちょっとやってみたい」と思っていただけるよう、 現場の感覚で、わかりやすくまとめました。
子どもたちの表情が変わる瞬間を、先生自身の喜びにつなげてほしい―― そんな願いを込めて、ここからご紹介します。
語り手の役割と使い方|劇の流れをやさしくつなぐ“橋渡し役”
語り手がいると、劇がぶれません。 場面の始まりと終わりをつなぎ、子どもたちが安心して演じられます。
- 先生が語っても、子どもが交代で語ってもOK
- 「おむすびは、ころころころりん…ぽとん!」など、語感のある言葉を使うと、物語が立ち上がります
- 語り手は、間(ま)をつくる人。急がず、ゆっくり語ることで、子どもたちの動きが生きてきます
- 先生が語り手になると、子どもたちは安心して動けます。 そして、先生自身も物語の中に入っていけます。
動きの工夫と場面の盛り上げ方|“やってみたい!”を引き出す演出
子どもは、動きがあると自然に集中します。 セリフだけでなく、体を使う場面をしっかりつくることが大事です。
- もちつき歌は、手拍子・太鼓・リズム遊びに展開できます
- おむすびが転がる場面は、布や玉を使って、実際に転がすと盛り上がります
- 猫の真似は、笑いと緊張を生む“山場”。大げさに演じると、観客も引き込まれます
感情を引き出すセリフと演技のヒント|“気持ちがわかる”から演じたくなる
子どもは、気持ちがわかると、自然に演技が深まります。 セリフの前に「どんな気持ちかな?」と問いかけるだけで、演技が変わります。
- 良いおじいさん:やさしさ・驚き・感謝
- 悪いおじいさん:欲張り・ずるさ・後悔
- ねずみたち:元気・警戒・怒り
- もぐら:静けさ・さみしさ・気づき
セリフは、子どもが言いたくなる言葉で。 「こらこら、待て待て〜!」 「ぺったん ぺったん ねずみのもちつき!」 「なんてことするの!追い出せ!」
「ぺったん ぺったん!」と声を合わせて動くだけで、子どもたちは夢中になります。 先生も一緒にやってみると、もっと楽しくなりますよ。
場面の切り替えとテンポのつくり方|飽きずに集中できる流れをつくる
劇は、テンポが命です。 長すぎると飽きる。短すぎると物足りない。場面の強弱をつけることで、集中が続きます。
- 楽しい(もちつき)→緊張(猫の真似)→静かな終わり(もぐら)という流れが理想
- 語り手がテンポを調整することで、子どもたちの動きが自然になります
- 動きとセリフのバランスを意識すると、観客も物語に入りやすくなります
「楽しい→びっくり→しんみり」――この流れがあると、子どもも観客も、最後まで引き込まれます。
まとめ|語りは、心を育てる“種まき”
昔話を語ることは、子どもたちの心に“生き方の種”をまくことです。 語りのあとに生まれる問い、感じたことを言葉にする時間、そして劇あそびへとつながる流れ―― それらすべてが、子どもたちの人格と感情を育てる土壌になります。
劇あそびは、ただ演じるだけの活動ではありません。 物語を感じ、自分の中に取り込んで、仲間と分かち合う時間です。 その中で、子どもたちは「どう生きたいか」を、少しずつ、自分の言葉で語り始めます。
私は、現場一筋で語り続けてきました。 そして今、次の時代に向けて、この知見を日本中に差し上げたいと思っています。
誠実な絵本と、誠実な語りがあれば、子どもたちは必ず感じて、考えて、育っていきます。 語りは、心を育てる。私は、そう信じています。
この台本と記事が、どこかの保育室や地域の集まりで、 子どもたちの笑い声と問いかけの時間につながっていくことを願っています。

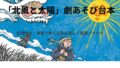
コメント