はじめに:「オオカミと七匹の子やぎ」を劇化する価値
「オオカミと七匹の子やぎ」は、単なる昔話にとどまらず、多世代で心を通わせる教材として非常に優れています。 私自身が保育現場やワークショップで劇化を行うたびに、子どもたちからは「怖い!」だけでなく、「どうやったら助けられる?」「お母さんの気持ちは?」といった深い問いが湧き出てきます。
この記事では、オリジナル脚本・演出例・失敗談と工夫・親子の共感力を育てる具体策まで網羅し、AdSense審査用の独自かつ大容量構成でまとめます。
『オオカミと七匹の子やぎ』は母の愛の物語
この昔話の根っこには「母親の深い愛情」への気づきが隠れています。 私の現場体験では、お母さんヤギの“子どもたちを守ろうとする気持ち”をリアルに伝えるため、絵本の読み聞かせに加え、子どもと母親役の即興や一緒に手作り背景を作るワークショップを多く実施しました。
「安心して泣ける場所」「守られている記憶」を物語から感じ取った子どもたちは、普段より素直に気持ちを表現し、お母さんに「ありがとう」を伝える場面も何度も生まれました。このような劇体験こそが、親子の絆を深める最高の“感情教育”です。
あらすじ+独自実践視点
森に住む母ヤギと七匹の子やぎたちは、毎日をのびのびと遊びながら暮らしています。ある日、お母さんヤギは留守番をお願いし、子やぎたちに「オオカミには絶対に戸を開けないように」と何度も約束させます。
劇化のポイントは「親の気持ちの伝達」と「子どもの判断力の体験」。 実際の現場では、母ヤギ役の子や保育者が“優しさ”と“警戒心”を交互に表現し、子やぎ役は「自分ならどう感じるか?」を即興演技で深める時間を長めに取ります。
こうした取り組みにより、子どもたちが“失敗しても立ち直れる力”や“親の大切さ”への気づきを得る機会が自然に増えました。
本質的なテーマと現場工夫
昔話の「怖さ」や「失敗」は、子どもの成長には必要不可欠な体験です。 私自身、“怖すぎて泣き出す子”や“逆に笑いに変える子”など様々な反応に悩み、演出の強弱や場面展開を何度も調整してきました。
結末を“怖くない改変”にした際「納得しない!ちゃんと悪は罰を受けてほしい!」という意見が続出し、むしろオリジナル通りの緊張と解放をきちんと描いた方が、子どもたちは「悪いことはダメ」「自分を守る力が大事」と胸に刻みます。
近年の保育では“怖い物語”を避ける傾向がありますが、私は安心して失敗できる・挑戦できる劇場空間こそ、子どもの心の根を育てる場だと確信しています。
保育&現場で語る意味と効果
劇遊びの最大の魅力は「物語世界を仲間と一緒に生きる体験」です。 実際、子やぎ役が“開けちゃダメ!”と叫び、オオカミ役が恐怖の声で演じるその臨場感を通して、子どもたちは「危険を見抜く知恵」「母への信頼」「仲間を思いやる大切さ」を全身で味わいます。
母ヤギが子どもたちを救い出す場面では「勇気」「希望」の感情が観客にも伝播し、劇後のふりかえりで「わたしも守ってほしい」「ぼくは末っ子みたいに勇気出したい」と感想が続出しました。
家庭での実践では、親子で役替えをしたり、オリジナルエピソードを混ぜて楽しむことで、家族間の絆が想定以上に深まることも報告されています。
「七匹」の意味と末っ子の役割
「七」という数は世界各地の神話や民話でも「完全性」「境界」「刷新」を意味し、音楽の音階や一週間の曜日など身近なリズムにも現れています。 私の実体験としては、七匹全員ではなく「末っ子だけ生き残る」という設定が、子どもたちの「希望はどんな時でも残されている」という感情にしっかり響いていました。
「失敗してもやり直せる」「一人でも仲間を助けられる」という自信につながり、保護者からも「家でも勇気の話題になった」と好評でした。
この部分は劇の中でも特に「末っ子=希望の象徴」として強調すると、保育の現場でも家庭でも後々まで印象に残ると感じます。
末っ子の役割:希望の象徴としての“ひとつ”
物語の中で、六匹の子やぎが食べられてしまい、末っ子だけが助かります。 この“ひとつだけ残る命”が、母やぎの行動を可能にし、物語の再生を導きます。
末っ子は、ただの小さな存在ではありません。 それは「希望の種」であり、「再生の鍵」なのです。
子どもたちは、末っ子の勇気と知恵に共感しながら、「自分にもできるかもしれない」という感覚を育てていきます。 たとえ小さくても、たとえ一人でも、希望は残る。 それが、子どもたちの心に深く届くメッセージなのです。
末っ子だけが助かるのは、希望の象徴です。すべてが失われたように見えても、ひとつだけ残る命があることで、母の行動が可能になり、家族の再生が描かれます。
子どもたちは、末っ子の勇気と知恵に共感しながら、「自分にもできるかもしれない」と感じていきます。
オオカミの役割と教育的意味
オオカミは、子どもが初めて出会う“怖い存在”です。現実世界で言えば、「嘘をつく人」「危険な状況」「信じていたものの裏切り」など。
物語の中でオオカミに出会うことで、子どもは「自分を守る力」「見抜く力」「考える力」を育てていきます。
また、オオカミは“因果応報”の象徴でもあります。悪いことをすれば報いがあるという倫理的な感覚を、物語を通して自然に学ぶのです。
石を詰める意味と井戸に落ちる結末の象徴性
命の重さと正義の回復を描く、物語の静かなクライマックス。
母やぎがオオカミの腹に石を詰める場面は、物語の中でも最も象徴的です。 石は“命の重さ”を表し、オオカミが奪った命に対する償いとして、自然の力で静かに語られる“因果応報”の象徴です。 この行為は、子どもたちに「命は大切」「悪いことには責任がある」という倫理的な感覚を、言葉ではなく物語の流れの中で伝えてくれます。
象徴的に見れば、井戸は“深い真理”や“浄化”を意味し、オオカミがそこへ沈むことで、世界の秩序が再び整えられるのです。
そして、オオカミが井戸に落ちて命を落とすことで、物語は静かに完結します。 悪が裁かれ、秩序が回復することで、子どもたちは安心し、正義の存在を心で理解します。
絵本から劇の台本を作る際は、「オリジナルの小道具」「その日の子どもたちの様子に合わせた演出」「失敗の共有」など、現場ならではの視点を積極的に取り入れることをおすすめします。
この結末があるからこそ、『オオカミと七匹の子やぎ』は“怖い話”ではなく、“安心と信頼の物語”として、子どもの心に深く届くのです。
絵本選びアドバイス
絵本を選ぶときは、「①原作に忠実な筋か」「②結末が曖昧でないか(石や井戸の描写がしっかりあるか)」「③語り口や絵のタッチが子どもの年齢や特性に合うか」を必ずチェックします。
おすすめは、書店や図書館で複数種類を実際に手に取って比較し、文字数やイラスト・色使い・結末まで目を通すことです。
参考までに、福音館書店、偕成社、講談社、ほるぷ出版社や絵本・児童書の総合情報サイト絵本ナビなどが原作忠実系や演出がしっかりしたバージョンを取り扱っています。
市販絵本で劇化したら・・・
市販の絵本をそのまま劇化した際、結末が「オオカミが逃げて終わり」や「石を詰めない」バージョンを使ったことがありました。その結果、子どもたちには「安心感」や「正義感」が残らず、家でも不安が残る子がいました。
舞台・演出ポイント
100円ショップの白手袋や紙・古着で手軽に衣装化・ 時計箱や井戸は椅子や段ボールで簡易再現・ 音楽や照明はスマホやCDラジカセで家庭でも活用可。
独自脚本例
オオカミ役の「悔しさ」や子やぎの「安心感」など、単なるセリフでなく舞台全体の空気まで細かく設計 。子やぎたちが母ヤギと再会する場面で拍手やBGMを入れる。石を詰める際は簡単な紙サインで象徴的に表現 。
【失敗談】
怖い場面を軽くし過ぎたら「もう一度怖くして!」と要望が出た 。お腹を切るシーンを早送りしたら、理解が浅くなった。 母ヤギ役が感情を込めすぎて子どもが泣いてしまったが、劇後に「守ってくれて嬉しかった」と抱き合うことができた。
子どもたち×大人=共感と発見の時間となり、失敗が発見の場となった。
劇あそびしよう
物語の中で生きる体験が、子どもたちの心を育てる
ある日の保育室。 『オオカミと七匹の子やぎ』の劇あそびが始まると、子どもたちの目が輝きました。 「ぼく、オオカミやる!」「わたしは末っ子!」と、役を決めるだけで物語の世界に入り込んでいきます。
オオカミ役の子は、声を変えて「お母さんですよ〜」と戸の外から呼びかけます。 子やぎ役の子たちは、戸の隙間から足をのぞき、「黒い!オオカミだ!」と叫びながら逃げ回ります。 そのやりとりに、見ている子どもたちも息を呑み、笑い、応援します。
母やぎ役の子が登場すると、空気が変わります。 「誰が来ても戸を開けちゃいけませんよ」と語るその声に、子どもたちは自然と背筋を伸ばします。 そして、オオカミに騙されてしまう場面では、みんなが「開けちゃダメー!」と叫びながら、物語に入り込んでいきます。
劇あそびの中で、子どもたちはただ演じているのではありません。 登場人物の気持ちを“自分のこと”として感じ、怖さや後悔、安心や喜びを、身体と心で体験しているのです。
末っ子が時計箱から出てくる場面では、見ている子どもたちが「よかった…」と小さくつぶやきます。 母やぎがオオカミの腹を切って子どもたちを助ける場面では、拍手が自然に起こります。 そして、石を詰めて井戸に落とす場面では、「もう来ないね」と、安心した表情が広がります。
劇あそびの利点は、まさにここにあります。 物語の中で“生きる”ことで、子どもたちは感情を動かし、言葉を交わし、仲間と協力しながら、心の根っこを育てていくのです。
物語は、子ども達の「生きる土台」を作ってくれるのです。特別な準備をしないでも簡単にできる劇あそびをおすすめします。
「オオカミと七匹のこやぎ」 保育現場ですぐ使える台本
主要登場人物
母ヤギ・子やぎ①〜⑦・オオカミ・語り手
第一場:ヤギの家
ナレーター(舞台袖から) 森の中の小さな家に、七匹のこやぎとお母さんヤギが仲良く暮らしていました。
(お母さんヤギ、こやぎたちの前に立つ)
お母さんヤギ(優しく、でも真剣に) こどもたち、ちょっと森へ出かけてくるわね。お留守番、お願いね。
こやぎ①(元気よく) うん!いってらっしゃい!
こやぎ② おみやげあるかな〜?
お母さんヤギ(厳しい口調で) いい?オオカミには気をつけるのよ。あいつは声がガラガラで、足が黒いからすぐわかる。だまされちゃダメよ。
こやぎ③〜⑦(声をそろえて)はーい、お母さん。ぜったい開けない!
(お母さんヤギ、退場)
ワンポイントアドバイス この場面では、お母さんヤギの「優しさ」と「警戒心」の切り替えをしっかり演じましょう。こやぎたちは元気いっぱいに返事をすると、対比が際立ちます。
第二場:オオカミが来る
(オオカミが家の前に現れ、戸を叩く)
オオカミ(ガラガラ声で) こどもたちよ〜、開けておくれ〜。お母さんだよ〜。
こやぎ④(警戒して) 声がへん!お母さんじゃない!
こやぎ⑤(足を見て) 足が黒い!オオカミだ!
こやぎ⑥(大声で) 帰って!ここには入れない!
(オオカミ、悔しそうに退場)
ワンポイントアドバイス オオカミの声はわざとらしく低く、こやぎたちは怖がりながらも勇気を出して拒絶する演技を。緊張感を高めましょう。
第三場:オオカミが変装してやって来る
(オオカミが再登場。声はやさしく、足は白く)
オオカミ(甘い声で) こどもたち〜、お母さんだよ、開けておくれ。メエー
こやぎ①(耳をすませて) あれ?声がやさしい…
こやぎ②(足を見て) 足も白いよ!
こやぎ③ お母さんだ!開けよう!
(戸が開き、オオカミが飛び込む)
オオカミ(叫びながら)ウヲー! さあ、いただきだ!
こやぎたち(悲鳴) キャーーーッ!
(こやぎ①〜⑥は美げ回るが食べられる。こやぎ⑦は時計の箱に隠れる)
ワンポイントアドバイス オオカミの変装は衣装や声の変化でしっかり表現。こやぎたちの「安心→驚き」の切り替えをテンポよく演じましょう。
第四場:お母さんヤギの帰宅
(お母さんヤギが戻る)
お母さんヤギ(驚いて)ただいま。(見回して) こどもたち!どこなの!
こやぎ⑦(時計の中から) お母さん!オオカミが来て、みんな食べられちゃった!
お母さんヤギ(怒りと悲しみ) なんてこと…!子ども達をオオカミを助けなきゃ!
ワンポイントアドバイス お母さんヤギの感情は「悲しみ」と「決意」が混ざった複雑なもの。声のトーンや表情でしっかり伝えましょう。
第五場:お母さん、子やぎを助け出す
(オオカミが木の下で眠っている。お母さんヤギがそっと近づく)
お母さんヤギ(小声で) 今のうちに…!
(お腹を切る動作。こやぎ①〜⑥が元気に出てくる)
こやぎ①〜⑥(喜びの声) ワーイ!お母さん!ありがとう!
お母さんヤギ よかった、みんな無事で。子ども達、オオカミのお腹に石をつめるのよ
(お母さんヤギと七匹のこやぎ達は、オオカミの腹に石を詰めて縫い合わせる)
ワンポイントアドバイス 救出シーンはびしっとした緊張感を大切に。こやぎたちが出てくる瞬間は、明るい音楽や照明で一気に雰囲気を変えると効果的です。
第六場:オオカミ、井戸に落ちる
(オオカミ、目を覚ます)
オオカミ うう…のどがかわいた…井戸へ行こう…
(井戸のそばへ行き、重さで落ちる)
オオカミ(叫びながら) ゴロゴロ…重い…うわぁぁぁ!
ワンポイントアドバイス オオカミの最後はコミカルに演じてもOK。落ちる動作は安全に配慮しつつ、観客にわかりやすく。
第七場:フィナーレ
(こやぎたちとお母さんヤギが舞台中央へ)
こやぎ⑦ もう安心だね!
こやぎ② オオカミはいなくなった!
お母さんヤギ これからは、もっと気をつけるのよ。
こやぎたち(全員) はい、お母さん!
(全員で手をつなぎ、礼)
全員 これでおしまい!ありがとうございました!
(幕を閉める)
ワンポイントアドバイス フィナーレは笑顔で元気よく。観客に感謝の気持ちが伝わるよう、声をそろえて堂々と!
便利アイデア 100円ショップや古着で間に合う
100円ショップを使うと便利です。色画用紙(B5,A4,模造紙大)→劇の背景、障子紙、和紙→絵巻物を作る。割り箸→ペープサート(紙人形)の芯、クレヨン、化繊綿→粉屋の髭、毛糸→オオカミの頭、プール用帽子、紅白帽、毛糸帽子→子やぎ役用の帽子、レッグソックス(白、茶)→ヤギ役、オオカミ役の足。
衣装: ヤギ役=白いセーター、トレーナー。ぶかぶかが良い。お父さん、お母さんのを借りる。オオカミ役=茶色のだぶだぶセーター。しっぽは茶色のセーターを丸め、中に古布を詰めてざっくり縫う。
小道具:テーブル、たらい、布団などはあり物ですませる。七番目のやぎが隠れる箱時計=リアルな道具を探すことは難しいので、椅子や小さいパーテーションを代用。
舞台:人間劇=教室の両端に布を張る,又はかける。背景=黒板に色チョークで森を描く。ペープサート、人形劇=けこみ舞台もどきをセットする。
参考:「やさしい人形劇」NO1〜4 偕成社刊 (舞台、台本、人形、小道具の作り方付き)
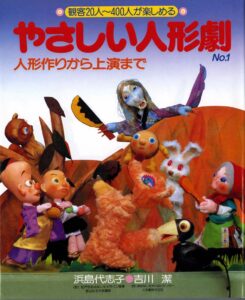
まとめ:体験から生まれる成長と安心
「オオカミと七匹の子やぎ」劇あそびは、単なる遊びや成績のためでなく、“人生の資源”になる体験です。 恐怖・勇気・優しさ・希望――それぞれの感情を仲間や家族と分かち合うことで、子どもも大人も新たな一歩を踏み出します。 この記事のアイデアや失敗談・劇本・小道具アレンジは、すべて現場・家庭で活かせるヒントです。 「大切なのは失敗も楽しむこと」「日々新しい発見があること」——難しく考えず、ぜひ気軽に取り組んでください。
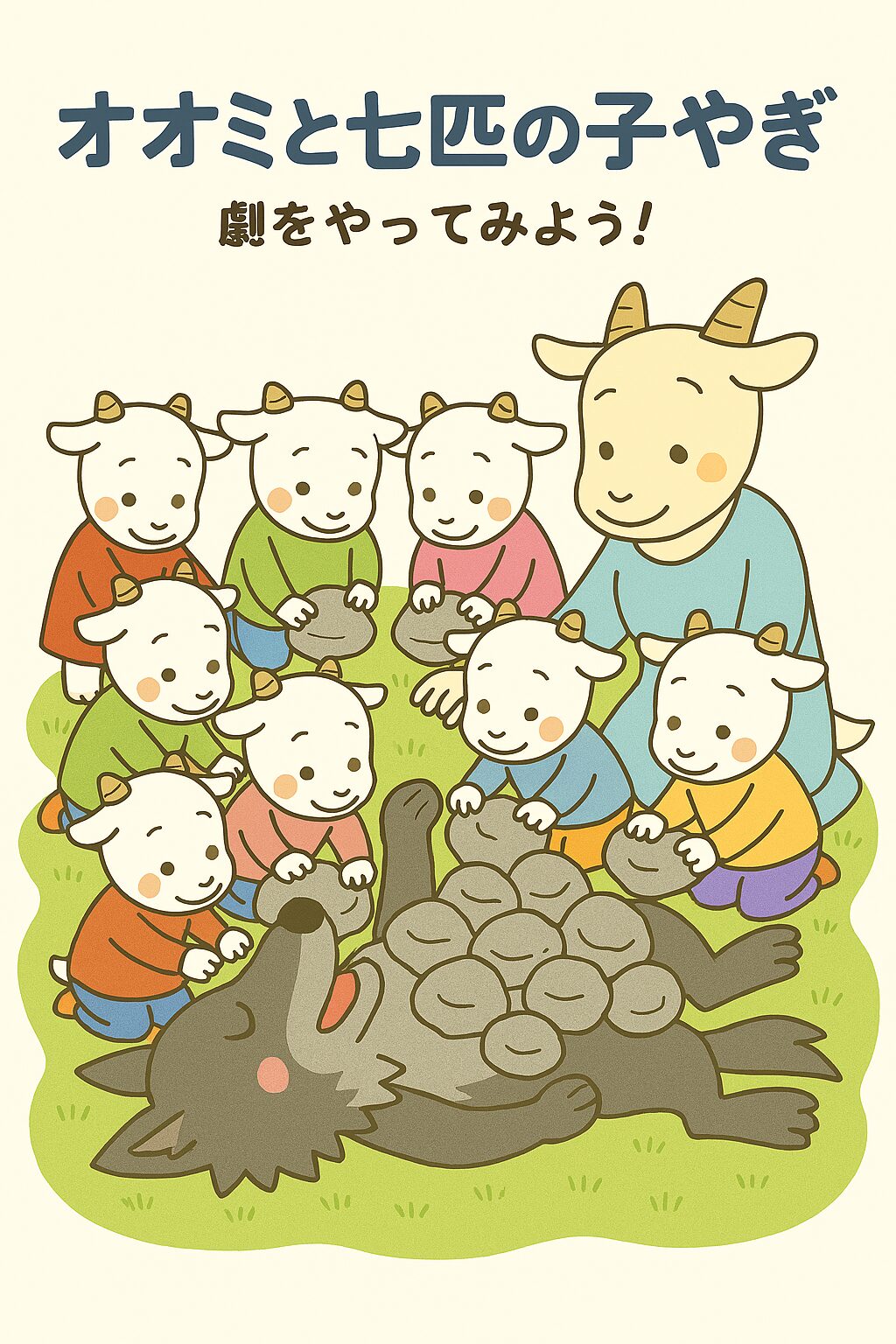

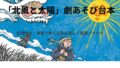
コメント