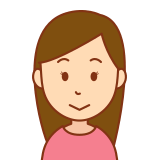
ミュージカル「アンデルセン」、これでいいのかしら?
創作に迷ったとき、なぜオーデンセだったのか
創作の手が止まってしまったとき、「自分は本当に物語を書く資格があるのだろうか」と、自分の足元そのものが揺らぐ瞬間があります。
そんな迷いを抱えていたある日、長年憧れていた童話作家アンデルセンの故郷・デンマークのオーデンセを訪ねることにしました。
この旅は、単なる観光ではなく、「物語はどこから生まれるのか」「現代の大人が童話を書く意味は何か」を確かめるための、小さなフィールドワークでもありました。
この記事では、オーデンセの街を一日かけて歩いた体験をもとに、創作に悩む人の視点から街の風景やスポットの回り方、そこで得た気づきを具体的に紹介します。
コペンハーゲンからオーデンセへ:創作ノートを抱えて移動
電車で約1時間半、物語の舞台へ
コペンハーゲンからオーデンセへは、国鉄DSBの長距離列車で向かいます。 中央駅でプラットフォームの電光掲示板を確認し、「Odense」方面行きの列車に乗れば、おおよそ1時間半前後で到着します。
車内には荷物棚やテーブル席もあり、ノートPCを広げてプロットを整理したり、アンデルセンの童話を読み返したりするのにちょうどよい環境でした。
チケットはDSB公式アプリや駅の券売機から事前購入が可能で、早めに手配すれば、通常料金よりも抑えた価格で手に入れられます。
「移動時間=下準備の時間」と考え、作品に登場させたいシーンを書き出しておくと、オーデンセに着いた瞬間から街の見え方が変わってきます。

コペンハーゲン中央駅からオーデンセへ 物語の旅は、ここから始まる。コペンハーゲン中央駅。
街の空気に少しずつ慣れてきたころ、私はふと足を止めました。 小さな路地の先に、どこか懐かしい気配を感じたのです。
その先にあったのは、アンデルセンの物語が生まれた場所――。
石畳とカラフルな家並みが迎えてくれる
まるで絵本の中に迷い込んだような街並み。アンデルセンの原風景がここにある。
オーデンセの旧市街は、大都市の喧騒から一歩離れた、時間の流れが少しゆっくりに感じられるエリアでした。
石畳の路地を進むと、黄色やくすんだ赤、淡いブルーなど、絵具で塗ったような家並みが続き、窓辺には季節の花がさりげなく飾られています。
脚本の視点で眺めると、「どの家の窓から物語の主人公が顔を出すのか」「路地の曲がり角でどんな出会いが起こるのか」と、街そのものが舞台装置のように見えてきました。
観光名所を効率よく回るよりも、「ここに住む子どもや親たちの日常」を想像しながら歩くことで、キャラクターの背景づくりに役立つ具体的なイメージが湧いてきます。
オーデンセで訪れたい!アンデルセンゆかりのスポット3選【モデルコース付き】
朝の光に導かれるように、私は旧市街の小道をたどっていきました。 石畳の先に現れたのは、まるで物語の扉のような建物。
ここから、アンデルセンの“はじまり”に触れる旅が始まります。
午前|博物館で感じた「脚本家としての答え」

物語の世界に入り込むような体験型ミュージアム。
午前中は、まずH.C. Andersen’s Houseへ向かいました。
日本の建築家・隈研吾氏の設計によって新しく生まれ変わったこの施設は、地上と地下が緩やかにつながる不思議な構造で、庭と展示空間が一体になったような感覚を味わえます。
館内では、音声ガイドや映像、立体的なインスタレーションが連動し、アンデルセンの人生と作品が「ひとつの長い物語」として立ち上がってくる構成になっていました。
舞台『アンデルセン』の脚本を書いたとき、幼いアンデルセンと両親が暮らした家の雰囲気を、写真と資料だけで想像しながら書いた場面があります。
実際に彼の幼年時代の家を訪れてみると、想像していた以上に天井が低く、家具も少なく、生活の気配が凝縮された空間で、「自分が舞台で描いた密度はそれほど外れていなかった」と感じることができました。
この「想像と現実のズレを確認する作業」は、創作に不安を抱える人にとって、大きな自己確認の時間になるはずです。
徒歩5分ほどの場所には、アンデルセンの幼年時代の家(Munkemøllestræde 3)もあります。 こちらは彼が2歳から14歳まで過ごした家で、当時の暮らしぶりがそのまま残されています。

アンデルセンの生家。とても小さい。ドアを入るとすぐ目に入るのが靴職人の道具。一人しか寝られないベッド、粗末な台所。

旧アンデルセン博物館への道に足跡。新しいアンデルセン博物館前にあるのか分かりませんが・・・。
実は、劇団天童の舞台では、アンデルセンの生家を舞台に、父・母・幼いアンデルセンの会話の場面を描きました。
その場面を創るとき、私は「本当にこんな空気だったのだろうか」と、どこかで不安を抱えていたのです。
けれど、実際にこの家に立ち、展示された家具や空間の静けさに身を置いたとき、あの舞台の記憶がふっと重なりました。 「
「ああ、私はお客様に嘘をついてなかった。これでよかった」と、胸の奥がじんわりと温かくなるような安堵を覚えました。
博物館を出たあとも、私はしばらくその余韻に包まれていました。 けれど、物語は建物の中だけにあるわけではありません。
アンデルセンが歩き、遊び、夢を見た風景が、街の中に今も息づいている――。 そう思った私は、川のほうへと足を向けました。
午後|オーデンセ川で確認した、舞台の一場面の「正しさ」
午後は、オーデンセ川沿いを歩きました。 水面には柔らかい光が揺れ、白鳥やカモがゆっくりと行き交い、その周りを地元の家族連れや学生たちが思い思いに散歩しています。
童話の舞台のような光景ではありますが、「絵本の中」と決定的に違うのは、その風景の中に現代の日常生活がしっかり流れていることでした。
保育園や学校で子どもたちと物語を一緒につくるとき、この川の記憶は強いヒントになります。
例えば「ただきれいな川」ではなく、「お母さんが洗濯する場所」「紙の船を流す遊び場」「ひとりで物語を考える秘密基地」といった複数の役割を持った場所として描くと、子どもたちの想像力が一段階深まります。
実際に洗濯石に触れたとき、「冷たい水の中で働く母」と「そのすぐそばで空想に浸る子ども」という対比が、舞台の一場面として頭の中で鮮やかに蘇りました。

オーデンセ川を流れる紙の船

アンデルセンの母が使った洗濯石。

アンデルセン博物館に展示されている絵。洗濯女として働く母。立っている子どもはアンデルセン。アンデルセン自身が描いた。

ミュージカル「アンデルセン」洗濯女の場
ミュージカル『アンデルセン』の中で、洗濯女として働く母と、川辺で人形劇に夢中になる幼いアンデルセンの場面を描きました。
母は冷たい川の中で一心に洗濯をし、アンデルセンは自作の人形を操って、歌を歌ったり、ひとり芝居をしたりして遊んでいる―― そんな情景を、私は想像で脚本に書き、舞台にしました。
劇団天童の公演ではこの場面が特に好評で、観客の心に深く残ったと聞いています。 けれど、私はずっと心のどこかで思っていたのです。
「あの場面、本当にあの子の記憶に近いのだろうか?」と。
今回、実際にオーデンセ川を歩き、母が洗濯をしていたという“洗濯石”に触れてみました。 苔むした石はひんやりとしていて、そこに膝をついて洗濯をしていた母の姿が、ふっと浮かびました。
そして、川辺の草むらに腰を下ろし、空を見上げながら人形を動かしていたであろうアンデルセン少年の姿も――。
「この舞台は、間違っていなかった」 そう思えた瞬間、私は静かに、でも確かに創作への安堵と誇りを感じていました。
想像で描いたあの場面は、大きく外れていなかった。 行ってよかった。そう心から思いました。

「ムンケ・モーセ公園 オーデンセ川沿い」 川沿いの公園で、物語の余韻に浸るひととき。
物語の余韻を胸に、私は静かな場所を求めて街の奥へと歩き出しました。 一日の終わりにふさわしい、静けさと物語が交差する場所へ――。
夕方|聖クヌーズ大聖堂とアンデルセン公園で考えた、作品を届ける相手

聖クヌーズ大聖堂(Sankt Knuds Kirke)
アンデルセンが堅信礼を受けた場所。静けさと荘厳さが共存する空間。教会の庭に大きなアンデルセン像が立っている。
旅の締めくくりには、聖クヌーズ大聖堂(Sankt Knuds Kirke)へ。 アンデルセンも訪れたとされるこの大聖堂は、荘厳で静謐な空間。 ステンドグラスから差し込む光が、心を落ち着かせてくれます。
その後は、アンデルセン公園へ。 園内には『人魚姫』や『裸の王様』など、彼の作品にちなんだ彫像が点在しています。
子どもたちが遊ぶ姿と、物語の登場人物たちが自然に溶け合う風景に、物語が生きていることを実感しました。

裸の王様

おやゆび姫

戦士

子どもに本を読むアンデルセン
公園のベンチに腰を下ろし、夕暮れの空を見上げながら、私は静かに思いを巡らせました。
子どもたちの笑い声、彫像のまなざし、教会の鐘の音―― それらがひとつに溶け合い、アンデルセンの物語が今もこの街で息づいていることを、私は確かに感じていました。
そしてその瞬間、私自身の創作の旅が、静かにひとつの答えにたどり着いたのです。
創作の旅としてのオーデンセ|私が得たもの
この旅で私は、アンデルセンの作品がどれほど彼自身の人生と結びついているかを、改めて実感しました。 彼の物語には、孤独、貧しさ、芸術への渇望、そして希望が込められています。
現地の学芸員や演出家の言葉からも、 「アンデルセンは童話作家というより、人生の語り部だった」という視点を得ました。
アンデルセンの足跡をたどることで、私は彼の物語の奥に流れる“沈黙の声”に耳を澄ませることができました。 それは、言葉にならない想い、誰にも届かないと信じていた祈りのようなもの。
けれど、彼はそれを物語に変え、子どもたちに手渡していったのです。 その姿勢に、私は創作の原点を重ねました。 そして今、旅の終わりに立って、私はこう思うのです――
まとめ|アンデルセンを“届ける人”にこそ訪れてほしい
オーデンセは、「童話の聖地」というよりも、「物語をつくる人の背中を静かに押してくれる街」だと感じました。
貧しさや孤独を抱えながらも、自分のなかに湧き上がる物語を手放さなかったアンデルセンの生き方は、現在進行形で創作に悩む私たちに、多くのヒントを与えてくれます。
もし、作品づくりに行き詰まり、自分の物語が薄っぺらく感じられるときは、一度「自分の原風景はどこか」「どの場所なら、あの日の自分と向き合えるか」を考えてみてください。
オーデンセへの旅は、その問いを投げかけてくれるきっかけであり、必ずしも現地に行けなくても、「自分にとってのオーデンセ」を探すことはできます。
この記事が、アンデルセンの故郷に興味のある方だけでなく、「物語を届ける立場として、次の一歩を踏み出したい」と願う方のヒントになれば幸いです。



コメント