それでも舞台は成功できる!ミュージカル『アンデルセン』初演を成功させた劇団代表が、キャスト募集から稽古の流れ、演出・振付の工夫、トラブル対応までを実体験に基づいて解説。
舞台づくりに悩む指導者必読のノウハウ記事を公開します。
はじめに|不安から始まった舞台づくり
「ミュージカルをつくってみたい。でも、私は素人だし、経験もないし…」 そんなふうに思って、最初の一歩を踏み出せずにいる方へ。
実は、私もまったく同じ気持ちでした。
劇団を持たず、演出も振付も初めて。
「失敗したらどうしよう」「プロから笑われるかもしれない」「先がないのでは…」 そんな不安でいっぱいの中、私はミュージカル『アンデルセン』の初演に挑戦しました。
でも、だからこそ言えるのです。 経験がなくても、仲間がいなくても、舞台はつくれます。 そして、つくった舞台は、想像以上に人の心を動かします。
この記事では、私が実際に経験した キャスト募集・稽古の進め方・演出と振付の工夫・トラブルの乗り越え方・本番の感動まで、 すべてを、これから挑戦するあなたのために書きました。
どうか、あなたの「やってみたい」が、形になりますように。 この文章が、その一歩を支える力になれたら嬉しいです。
私自身、「仲間がいない」と思っていた時期がありました。 でも、舞台づくりを通して気づいたのです。
仲間は“いる”のではなく、“なっていく”ものなのだと。 この気づきは、人生において大きな収穫でした。
舞台を終えたとき、私は初めて「自信」というものを手にした気がします。
キャスト募集の方法とポイント
劇団を持たない人でもできる!
出演者は、学生・一般の方・子どもたち。演技経験も年齢もさまざまでした。 キャスト募集は、以下の方法で行いました。
- 地域の市民センターにチラシ掲示
- SNS(Facebook・Instagram)で「未経験歓迎」の投稿
- 小学校・中学校・高校に協力依頼(保護者向けプリント)
- 口コミと紹介
ポイントは、「演技経験不問」「一緒に舞台をつくりましょう」という安心感のある言葉を使うこと。
また、オーディションではなく「顔合わせ+読み合わせ」で選ぶことで、緊張せずに参加できる雰囲気を大切にしました。
練習初日|戸惑いと緊張をどうほぐしたか
読み合わせで見えた不安
配役を発表し、いざ稽古開始。 台本の読み合わせでは、学生メンバーや未経験の大人が本当に緊張していました。
舞台設定やキャラクターの意図がなかなか伝わらず、「自分は台詞を覚えるのが精一杯」という声も。
場の空気をほぐす工夫|絵本と即興で心が開いた瞬間
初めての稽古の日。 配役が決まり、台本を手にしたものの、稽古場にはどこか緊張した空気が漂っていました。
セリフを読む声も硬く、動きもぎこちない。 「このままでは、物語の世界に入っていけないかもしれない」
――そう感じた私は、ある工夫を試してみました。
まず、アンデルセンの時代背景や童話の世界観を、イラストや小道具を使って視覚的に伝えることにしました。
特に効果的だったのは、アンデルセン作の絵本の読み聞かせです。
『雪の女王』『人魚姫』『みにくいあひるの子』―― どれも本格的で芸術的な絵本で、舞台に登場する場面がふんだんに描かれているため、 俳優たちは自然と物語の世界に引き込まれていきました。
さらに、稽古の最初には毎回、簡単な遊びや即興のやりとりを取り入れました。
たとえば、役になりきって一言だけ話す「一言即興」や、動きだけで感情を伝える「ジェスチャー遊び」など。
笑いが生まれ、声が出て、目が合って、空気がゆるんでいくのがわかりました。
このちょっとした取り組みで、稽古後にはこんな感想が聞かれました。
「みんな別人のように肩の力が抜けた」 「安心して声が出せるようになった」 「物語に入るのが楽しくなった」
舞台づくりは、技術の前に“心の準備”が必要なんだと、改めて感じた瞬間でした。
歌とダンス|つまずきポイントの乗り越え方声が揃わない・振付が難しい|“できない”の声と向き合った日々
歌稽古が始まると、まず譜面を読むことに戸惑う子どもたちがいました。
特に小学生は、音符の意味がわからず、スタッフが一人ひとりに寄り添って教える場面も多くありました。
三部に分かれてのパート練習では、隣の人の声につられて自分の音程が取れないことも。
そんなときは、少し距離をとってパートごとに分かれて練習し、最後に合唱へとつなげていきました。
それでも、声が揃わないことはよくあります。 私は「それがふつう」と思うようにしています。
最初から完璧に揃うことはなく、“揃っていく過程”こそが舞台づくりの醍醐味なのです。
一方、ダンスの振付ではさらに難しさがありました。
全員が同じ振り付けではなく、歌のパートに合わせて動きも変わる構成だったため、「できない」「やりたくない」「難しい」「降りたい」――そんな弱音が次々と出てきました。
率直に言って、私自身も「これはマズい。本当に本番に間に合うのか?」と不安になりました。
でも、そこで諦めずに、一人ひとりの“できるところ”を見つけて、少しずつ積み上げていくことにしました。
できないことを責めるのではなく、 「ここまでできたね」「この動きはきれいだったよ」と、できたことに光を当てる。
それが、子どもたちの表情を変え、動きを変え、声を変えていきました。
歌詞の意味と感情を共有|“一緒に動く”から生まれる表現
歌と振付がうまくつながらない――そんな悩みが出てきた頃、私は振付師とじっくり話し合いました。
「この歌は、どんな気持ちで歌うのか?」 「キャラクターは、どんな表情で、どんな動きをするのか?」
そこで決めたのは、歌詞の意味と感情を、ひとつずつ丁寧に共有すること。 そして、俳優と一緒に動くこと。 指示するのではなく、共につくりあげる姿勢です。
たとえば――
「ここは笑顔になる場面。喜びがあふれてるから、顔を観客に向けて」 「泣き顔の場面は、斜め下を見て、涙をこらえるように」 「右手を斜め上、目線は指の先を見る。希望を描く動きだね」
「舞台中央まではツーステップ。軽やかに、でもしっかり前へ」 「喜びの顔は、ちゃんと観客に見せよう。伝えるためにね」
こんなふうに、歌詞の一行ごとに“気持ち”と“動き”をつなげていく。
そして、私自身が俳優たちと一緒に動きながら、「この動き、どう感じる?」「もっとこうしてみようか」と声をかけていく。
すると、メンバーの歌が変わりました。 動きが変わりました。 そして、俳優たちの表情が、舞台の空気を変えていったのです。
舞台は、誰かが“教える”ものではなく、みんなで“つくる”もの。 そのことを、私はこの稽古で改めて教えてもらいました。
動画でつながる稽古|“宿題制”から始まった自発の連鎖
歌稽古、振り付け、芝居―― どれも一度の稽古では覚えきれない。 そこで私は、稽古風景をスマホで撮影し、家で自主練できる“宿題制”を導入しました。
動画は、メンバー全員が見られるようにグループLINEを作成。
子どもたちは家庭で親と一緒に確認でき、 社会人メンバーは通勤電車の中で繰り返し見られる。 文明の利器を最大限に活用した、時間を選ばない稽古です。
最初は「宿題」として渡していた動画も、 次第に「自分の出演場面を撮ってほしい」と頼まれるようになりました。
ある子は、動画を見てこう言いました。「できてると思ってたけど、全然できてなかった…」 「こんな姿を観客に見せたくない。もっと練習したい。」
自分の姿を客観的に見ることで、意識が変わる。 そして、意識が変わると、舞台は自然と動き出すのです。
公演後のアンケートには、こんな声が寄せられました。
「自主練があったからついていけた」 「みんなで助け合う雰囲気が良かった」 「動画で確認できたから安心して本番に臨めた」
“宿題”だったはずの動画が、いつの間にか“自分の武器”になっていた。 それは、舞台づくりが“教える”から“育ち合う”に変わった瞬間でもありました。
照明と小道具|低予算でも雰囲気を出す工夫
“海”の場面をどう再現したか
人魚姫の海の場面をどう“舞台上で再現”すればいいか悩みました。
業者に頼める大掛かりな舞台セットは予算的に現実的でなかったため、 「ブルーの布」「手作りの泡ベース小道具」「LEDライト」をホームセンターと100均で調達。
演技中、スタッフが舞台上手袖と下手袖に薄い水色の布を手の持ち、ゆっくり上下に動かし、泡を投げ入れることで「海底っぽい雰囲気が出た!」と狙い通りの演出に。
保護者や観客からも「こんなセットでここまで雰囲気が出せるんですね」と驚きの声がありました。
(ヒント)薄い布の幅、100cmから140cm。広幅が良い。布を揺らすスタッフは上下共に黒い服。
練習中のトラブルとその解決
やる気の低下と意見の対立
中盤に差しかかった頃、稽古場の空気が少しずつ変わってきました。 「やる気が落ちてきた」「意見の食い違いで練習が止まる」――そんな場面が増えてきたのです。
ある日、リーダー格の俳優がぽつりとつぶやきました。「…やってられないよ。」
その瞬間、セリフも動きも止まり、稽古場に緊張が走りました。 俳優たちは無言のまま立ち尽くし、空気が張りつめていくのがわかりました。
こんなとき、演出家がピリピリした顔をしてしまうと、火種が広がります。 私はぐっとこらえて、わざと明るい声で言いました。
「お疲れ様、休憩10分にしましょう!」
そして、リーダー格の俳優の隣にそっと座り、こう話しかけました。「良い意見を持っているみたいだね。聞かせてくれる?」
その間、他の俳優たちが固まって不満を言い合わないよう、スタッフにも目配りをお願いしました。 小さな火種が大きくなると、グループが分裂することもあるからです。
このときの対応が功を奏し、リーダー格の俳優は冷静さを取り戻し、 その後の稽古では、むしろ全体をまとめる存在になってくれました。
個別ヒアリングと再検討|“心を聞く”ことで舞台が動き出す
ある時、稽古場の空気が重くなり、意見の食い違いや不安が表に出始めました。
このままでは、舞台が崩れてしまうかもしれない――そう感じた私は、全キャストとスタッフに個別ヒアリングを実施することにしました。
グループでのヒアリングでは本音が出ません。だから一人ずつ気持ちを聞くことが大事です。
一人一人と顔を合わせて話せば食い違い、思い違い、気持ちのすれ違い、俳優も演出家も良い舞台を作りたいtという一心でやっていることをお互いに確認し合いました。
人間同士の心の深い理解ができる。それなしにはアンデルセンは作れないと確信。メンバーと話せたことは私の宝物。その後もメールのやりとりなどで長い付き合いが続いている。
本番直前と当日の“ドラマ”
ゲネプロの不安と本番の奇跡|舞台が人を変える瞬間
ゲネプロ――本番同様の通し稽古。 セリフを忘れる、立ち位置を間違える、出はけの方向が逆、音程が外れる…。
「これで本番、いけるのか…?」 私は袖で見ながら、内心ヒヤヒヤしていました。
でも、本番当日。 舞台袖に集まった子どもたち、学生、サラリーマンたちの顔が、いつもと違って見えました。
キリッとした目。 覚悟のある表情。 楽屋から小走りで舞台に向かう姿。 袖で静かに待機する背中。 まるでプロの俳優のような顔つき。
「こんな顔するんだ…」 私は思わず見とれてしまいました。 人は、舞台で変わるんだ。
袖で目が合う。 舞台の上でも、見合わせる顔と顔。 誰かが小さくつぶやいた。「今までの稽古が全部つながった…!」
セリフの間合い。 動きのタイミング。 歌の感情。 すべてが、これまでの積み重ねの中から自然に生まれていました。
そして―― 幕が降りた瞬間。
涙でハグする子。 笑顔でハイタッチする学生。 「やったね!」「ありがとう!」
この舞台を一緒につくったという実感が、全員の中にしっかり根づいていました。
観客アンケートには、こんな感想が並びました。
「後半から涙が止まらなかった」 「小劇団とは思えない一体感」 「子どもたちの表情が本当に生きていた」
それは、舞台の成功以上に、心の交流が生まれた証だったと思います。
誰でも、初めては怖いものです。
でも、「案ずるより産むが易し」と言います。 ぜひ、トライしてみてください。 全く別世界が開けます。 そして、そこには、あなた自身の新しい顔が待っています。
まとめ|舞台づくりは“仲間になる”旅。そして、アンデルセンの魔法をあなたへ
失敗もありました。 不安も、衝突も、涙もありました。 でもそのすべてが、「現場の小さな工夫」と「乗り越えた体験談」として積み重なり、 本当に価値のある舞台を、みんなでつくることができました。
舞台づくりで悩んでいる方へ。
「どこから始めたらいいかわからない」――そんな気持ち、私もずっと抱えていました。 でも、始めてみれば、必ず道は開けます。
それぞれの劇団、それぞれの現場には、その場所にしかない個性と強みがあります。 それを活かして、ぜひ挑戦してみてください。
私がこの舞台で得た一番の宝物は、“仲間になる”という経験でした。 最初は「誰もいない」と思っていた。
でも気づけば、一緒に悩み、笑い、支え合う人たちがそばにいた。 この気づきは、人生において大きな収穫であり、私自身の自信にもつながりました。
そして―― アンデルセンという作家の魅力を、もっと多くの人に届けたい。 彼の物語は、子どもにも大人にも、心の奥に届く力があります。
『雪の女王』『人魚姫』『みにくいあひるの子』―― どれも、人間の弱さと強さ、孤独と希望を描いた、深く美しい物語です。
ミュージカルは、演劇の中でも最高の表現手段だと私は思っています。
歌・ダンス・芝居――すべてが融合して、観客の心に直接届く。 だからこそ、プロだけでなく、誰にでもやってほしい。
子どもでも、初心者でも、地域の仲間でも。 舞台は、誰にでも開かれています。
もし「やってみたい」と思った方がいたら、 台本も、演出も、振付も、必要なら私が手伝います。
一緒に考え、一緒につくり、一緒に舞台を育てましょう。
あなたにも、きっと仲間が生まれます。 そして、あなた自身が誰かの仲間になる日が、必ず来ます。
舞台は、人生を変える力を持っています。
どうか、あなたの「やってみたい」が、形になりますように。 この文章が、その一歩を支える力になれたら、私は本当に嬉しいです。

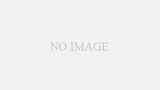
コメント