『北風と太陽』を劇あそびに!台本・演技指導の実践例で、子どもの心と表現力を育てるヒントが満載です。
「劇あそびにぴったりな題材って、どう選べばいい?」「子どもたちが楽しみながら、心も育つ活動がしたい」――そんな先生方の声に、現場歴55年の私がお応えします。
今回ご紹介するのは、イソップ寓話『北風と太陽』を使った劇あそびの実践例です。力と優しさの違いを描いたこの物語は、子どもたちの感情表現や協調性を自然に育ててくれます。
この記事では、台本の工夫・演技指導のポイント・子どもたちの実際の反応を、すべて現場目線で具体的にお伝えします。保育・教育の現場ですぐに使える内容を、ぜひご活用ください!
『北風と太陽』は劇あそびに最適な題材です
物語の教育的価値と演劇的魅力
『北風と太陽』は、子どもたちに「力で押すこと」と「やさしく包むこと」の違いを、体で感じさせてくれる物語です。北風は「ビューッ!」と吹き飛ばそうとするけど、旅人はコートをぎゅっと握って離さない。一方、太陽は何も言わずに、ただぽかぽかと照らすだけ。それだけで旅人は自分からコートを脱ぐんです。
この展開を劇あそびにすると、子どもたちは自然と「どうすれば相手が気持ちよく動いてくれるか」を考え始めます。ある年長の男の子は、北風役で「もっと強く吹いたら脱ぐかも!」と全力で走り回っていました。
でも、太陽役の女の子が静かに笑顔で手を広げると、旅人役の子が「なんかあったかい…」とつぶやいて、そっとコートを脱いだんです。
この瞬間、力と優しさの違いを、言葉じゃなく体で理解しているんですよね。
しかもこの物語、登場人物が少なくて展開もシンプルだから、年少さんでも取り組めます。動きが中心の子には北風を、表情で語れる子には太陽を。旅人はどちらの気持ちも受け止める役なので、感受性のある子にぴったりです。
動き・声・表情――どの子にも「自分らしく演じられる場所」があるのが、この作品の魅力です。
演劇教育における活用ポイント
『北風と太陽』を劇あそびにすると、子どもたちは自然と感情を表すことの面白さに気づいていきます。北風になって「怒ってる風」を表現する子もいれば、太陽になって「優しい気持ち」を笑顔で伝える子もいます。感情表現の幅が広がるんです。
演じながら、「どう言えば伝わるかな?」「どんな動きをすれば旅人が反応するかな?」と、子どもたちは対話の力を育てていきます。セリフだけじゃなく、目線や間の取り方にも気づき始めるんですよ。
そして何より、「北風と太陽、どっちをやりたい?」と聞くと、子どもたちは自分で選びます。自分の役割を選ぶことが、物語への責任感につながるんです。「ぼくが北風だから、ちゃんと吹かないと旅人が脱がない!」なんて言葉が出てくると、もう立派な演者です。
この物語は、一人語りでもグループ劇でも展開できるのが強みです。少人数のクラスなら先生が語り手になって、子どもたちが動きで表現するスタイルもおすすめ。人数が多ければ、風の精や光の精など役を広げて、みんなで物語をつくることができます。
物語の流れを感じながら、自分の役割を果たす――その体験が、子どもたちの心をぐっと育ててくれるんで
現場での子どもの反応と成長の記録
実体験から見えた子どもの表現力
『北風と太陽』を劇あそびにすると、子どもたちは本当に生き生きと動き出します。ある年中の男の子、北風役を任された瞬間に「もっと強く吹きたい!」と叫びながら、腕をぐるぐる回して全力疾走。風になりきって、顔まで真剣そのもの。全身で“吹く”ことに挑んでいる姿は、まさに演劇の原点です。
太陽役の女の子は、最初は照れていたけれど、「笑顔であたためるって楽しい」と言いながら、静かに手を広げて旅人を見守るようになりました。先生が「太陽は怒らないよね」と声をかけると、「うん、優しく見てるだけ」と答えて、表情にしっかり気持ちを込めるようになったんです。
旅人役の子も負けていません。「寒いからコートは脱がないよ」と自分でセリフを考え、「あったかくなったら脱ぐね」と、太陽の演技に合わせて動きを変えていく。物語の流れを感じながら、自分の演技を組み立てているんです。
こういう瞬間に、私はいつも思います。 子どもって、ちゃんと物語を“生きて”いる。 こちらが本気で向き合えば、子どもたちはそれ以上の力で応えてくれる。 だからこそ、劇あそびは教育の現場に必要なんです。
劇あそびを通じて育つ力
劇あそびには、子どもたちの力を引き出す“育ちの種”がぎっしり詰まっています。『北風と太陽』のような物語を演じることで、自分の気持ちを声や動きで伝える「自己表現力」が自然に育ちます。
北風が吹くタイミング、太陽が照らす間――それぞれの役が関わり合うから、「相手の動きを見て、自分がどう動くか」を考える「協調性」も身につきます。台詞を覚えるだけじゃなく、「こう言ったら旅人が反応するかな?」と考える姿には、創造力の芽がしっかり育っているのが見えてきます。
そして、何より嬉しいのは、普段あまり話さない子が、役を通して声を出し始める瞬間です。セリフは短くても、自分の役割があることで「伝えたい」という気持ちが湧いてくる。演じることが、自信につながるんです。
さらに、北風の気持ち、太陽の気持ち、旅人の気持ち――それぞれを演じることで、他者の感情に触れ、理解しようとする力も育ちます。 「怒るってこういうことか」「優しくするって、こういう感じなんだ」――そんな気づきが、子どもたちの中にしっかり残っていきます。
劇あそびは、遊びじゃない。心を育てる、立派な学びの時間です。
台本と演技指導で劇あそびをもっと楽しく
『北風と太陽』劇あそび台本と演技指導|年中〜小学校低学年向け・教育現場で使える実践例
登場人物(基本構成)
- ナレーター(先生または子ども)
- 北風
- 太陽
- 旅人 ※追加可能:風の精(2〜3人)、光の精(2〜3人)、雲、木々、空の声など
シーン1:空の上の対立
ナレーター(静かに語り始める) 空のずっと上――風がうなり、光が揺れる場所で、北風と太陽が向かい合っていました。 ふたりは、いつも言い合いばかり。どちらが強いか、決して譲らないのです。
北風(腕を組み、声を張って) 強さってのは、吹き飛ばす力だ!ぼくの風が空を動かし、木々を揺らす! おまえのぬるい光なんか、ただの飾りだ!
太陽(静かに、でも鋭く) 強さとは、心を動かす力。 わたしの光は、花を咲かせ、命を育てる。 あなたの風は、ただ壊すだけ。
北風(一歩前に出て) 壊す?ふざけるな!ぼくの風がなければ、空は止まる! さあ、勝負だ。どちらが“本当に強い”か、決めようじゃないか!
太陽(ゆっくりと立ち上がり) いいわ。力を見せるのではなく、心に届く力を試しましょう。 あそこに、旅人が歩いている。 そのコートを、どちらが先に脱がせられるか――それで決めましょう。
ナレーター こうして、空の上で始まったのは、力とやさしさの勝負。 北風と太陽――ふたりの強さが、旅人の心に試される時が来たのです。
シーン2:北風の挑戦
ナレーター 北風は、空の奥から力を集めました。 「今こそ、ぼくの風を見せるときだ!」――その風は、山を越え、木々をなぎ倒すほどの勢いでした。
北風(全身を使って、叫ぶように) うぉぉぉーーーっ!!これがぼくの本気だ!逃げられるものか!
風の精たち(走り回りながら) ビューッビューッ!もっと吹けー!もっと強く!
旅人(帽子を押さえ、コートを抱えながら) うわっ…風が痛い…目も開けられない…でも…脱いだら…凍えてしまう…
ナレーター 旅人は、風に押されながらも、コートをぎゅっと抱きしめて歩き続けました。 北風の力はすさまじく、空も地面も震えていました。 でも――旅人のコートは、脱げませんでした。
北風(肩を落とし、悔しそうに) なんでだ…こんなに吹いてるのに…ぼくの力じゃ、心には届かないのか…
シーン3:太陽の挑戦
ナレーター 風が静まり、空にあたたかな光が広がりました。 太陽は、何も言わずに、ただ旅人を見つめていました。
太陽(静かに、でも確かな声で) ぽかぽか、ぽかぽか… あたたかさは、急がない。 心まで届くように。
光の精たち(ゆっくり回りながら) ぽかぽか〜 ぽかぽか〜
旅人(顔を上げて、ゆっくりと動き始める) あれ…さっきまで寒かったのに… なんだか…あたたかい…風じゃない…光だ…
ナレーター 旅人は、コートの前を開きました。 そして、ゆっくりと、コートを脱ぎました。 その顔には、安心と、少しの笑顔が浮かんでいました。
旅人(嬉しそうに) あったかい…気持ちいい… 川の水もきっと、あたたかいだろうな…
(旅人、ゆっくりと川へ向かい、服を脱いで入る動作)
旅人(手を広げて) はぁ〜…生き返るようだ…
シーン4:結末(交わらないふたり)
北風(遠くから見つめながら、低く) ふん…コートを脱がせるだけが目的じゃない。 ぼくは、動かしたかった。揺さぶりたかった。 それが届かないなら、それでいい。
太陽(静かに、でもはっきりと) あなたの風は、強い。 でも、心は…力では動かない。 人の心を溶かすのは、愛よ。
北風(背を向けながら) 愛なんて、風には見えない。 ぼくは、ぼくのままで吹き続ける。
太陽(空を見上げて) そして私は、照らし続ける。 誰かの心に届くまで。
ナレーター(余韻を込めて) ふたりは、交わらないまま、それぞれの空へ戻っていきました。 風は吹き、光は差す―― でも、旅人の心に残ったのは、あたたかさでした。
旅人(静かに) ありがとう… ぼくの心を動かしたのは、やさしさだった。
全員(静かに並び、手はつながず) おしまい。
台本の工夫と提供について
『北風と太陽』の劇あそび台本は、セリフはとにかく短く、動きで伝える構成にしています。たとえば北風は「吹き飛ばしてやるぞ!」、太陽は「ぽかぽかしてきたよ」といった一言で十分。言葉に頼りすぎず、体で語ることを大切にしています。
旅人は「寒いな…」「あったかくなった…」と、状況に合わせてつぶやくだけ。セリフが少ないからこそ、子どもたちが自分のタイミングで動けるんです。言葉が苦手な子も、動きでしっかり参加できます。
そして、人数が多いクラスや、もっとみんなで楽しみたいときは、「風の精」「光の精」「雲」「木々」などの役を追加します。風の精は北風の応援隊、光の精は太陽の仲間。雲は空を覆ったり、木々は風に揺れたり――どの役も、動きで表現できるから、年少さんでも安心して参加できます。
実際に、風の精を演じた子が「ビューッって一緒に吹くの楽しい!」と笑顔で走り回っていたり、木の役の子が「風が来たらゆれるんだよね」と自分で動きを考えたり――役があることで、子どもたちの想像力がどんどん広がっていくんです。
台本は、先生のクラスの人数・年齢・目的に合わせて調整できます。 「年少さんだけどやってみたい」「発表会で使いたい」「保護者参加型にしたい」――どんなご希望でも、すぐに対応できます。希望があれば、台本はすぐにお渡しできますし、演技の流れや構成も一緒に考えます。
子どもたちが“自分の役”を持って、心から楽しめる劇あそびを届けたい。 それが、私の台本づくりの原点です。
演技指導のポイント
演技指導って、難しく考えなくて大丈夫です。子どもたちが「なりきる」ことを楽しめれば、それがもう立派な演技なんです。
たとえば北風。「腕を広げて走ってみよう!」と声をかけると、子どもたちはビューッと風になって走り回ります。「もっと強く吹いてみようか?」と言えば、「うぉー!」と叫びながら全力疾走。声の強さと動きで、風の勢いを体で表現するんです。ここで大事なのは、「正しく」じゃなく「楽しく」吹くこと。風になりきる喜びを味わわせてあげてください。
太陽は、まったく逆。「笑顔で、ぽかぽかって伝えてみよう」と言うと、子どもたちは静かに手を広げて、優しい声で語りかけます。「怒らない太陽ってどんな顔?」と聞くと、にっこり笑って「あったかくしてるよ」と言ってくれる。静かな動きと優しい声が、太陽の“あたたかさ”を伝える演技になるんです。
旅人は、状況に応じて動きを変える役。寒いときはコートをぎゅっと抱えて、あたたかくなったらそっと脱ぐ。セリフは「寒いな…」「あったかくなってきた…」だけでも十分。自分でタイミングを考えて動くことで、判断力や物語の理解が深まります。
そして、人数が少ないクラスや、子どもたちがまだ慣れていない場合は、ナレーション形式がおすすめです。先生が語り手になって、「北風がビューッと吹きました」「太陽がぽかぽかと照らしました」と語ることで、子どもたちは動きに集中できます。語りのテンポが物語のリズムを作り、子どもたちの演技を支える土台になります。
演技指導は、正解を教える場ではなく、子どもたちの“感じる力”を引き出す場です。 「その風、すごく強かったね!」「太陽の笑顔、旅人が安心してたよ」――そんな声かけひとつで、子どもたちはどんどん自信を持って演じてくれます。
子どもたちの中にある“表現したい気持ち”を、そっと後押しする。 それが、先生の演技指導のいちばんの力です。
まとめと先生方へのメッセージ
『北風と太陽』で広がる演劇教育の可能性
- 北風と太陽』は、ただの昔話じゃありません。子どもたちの心の動きや、表現する楽しさをまるごと体験できる劇あそびの宝物です。風になって走る、太陽になって笑う、旅人になって感じる――その一つひとつの動きの中に、子どもたちの「伝えたい」「感じたい」という気持ちがちゃんと育っていきます。
- 「うちのクラスでもできるかな?」と思った先生、大丈夫です。台本は年齢や人数に合わせて調整できますし、演技の流れや指導のポイントもすべてご相談いただけます。 「年少さんだけどやってみたい」「発表会で使いたい」「保護者も巻き込みたい」――どんな現場でも、一緒に考えて、一緒につくっていけます。
- 劇あそびは、特別なスキルがなくても始められます。必要なのは、子どもたちの表現を信じる気持ちと、先生のちょっとした勇気だけ。一緒に、子どもたちの「演じる力」と「感じる力」を育てていきましょう。 その先には、きっと、子どもたちの心が動く瞬間が待っています。
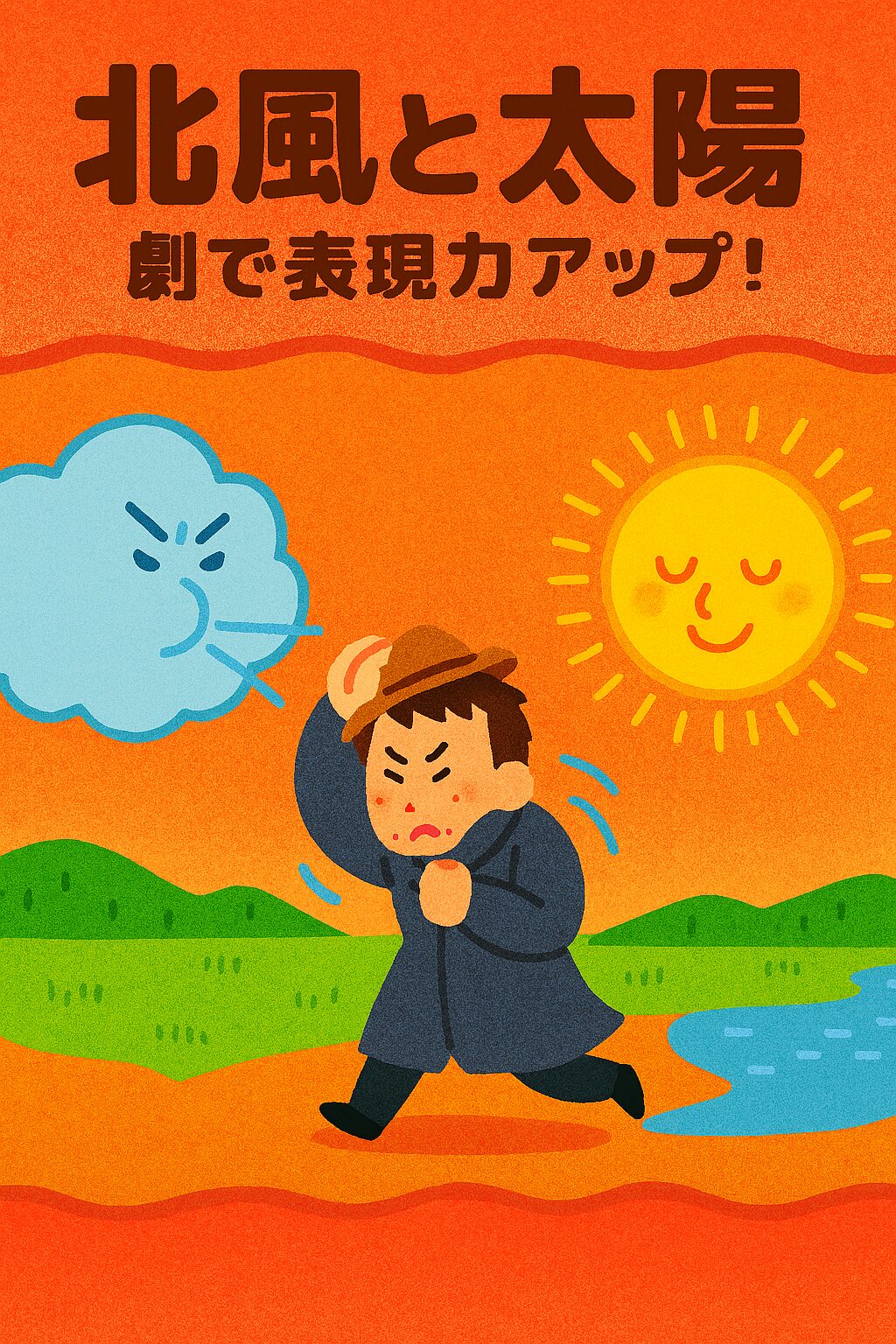

コメント