はじめに|物語を通して見つける“犠牲”の本質
アンデルセン童話をじっくり読み進め、語り部として舞台を作ってきた私は、登場人物たちの“犠牲”には独自の美しさがあることに気づき始めました。
彼らが何かを手放すとき、それは誰かの期待や社会のルールに従うためではなく、内なる願いと向き合う時間のようにも感じます。子どもにとっても大人にとっても、物語がそっと問いかけてくる“生き方のヒント”を一緒に考えてみましょう。
『人魚姫』ー声を捨ててでも叶えたい夢とその勇気
人魚姫は、魔女によって声を失いながらも、自分の意思で人間の世界へ歩み寄ろうとします。王子への一途な想いだけでなく、「自分自身の可能性を試したい」という純粋な衝動がこの選択には込められていると感じます。
声を失うことで思いを伝えられずに悩み苦しみますが、その姿は“犠牲”というよりも“心から決めた挑戦”のようでもあります。物語の中で、語り芝居として子どもたちに伝えたいのは「大切なものを失っても、自分の選んだ道に誇りを持つこと」の大切さです。
「ひたむきな心が生む感動──劇づくりの始まり」
アンデルセンの原作に忠実な絵本を子どもたちに初めて読み聞かせたとき、物語のラストまで静かに耳を傾ける真剣な眼差しに心を打たれました。
純粋な気持ちが子どもに届き、語り手として舞台でそのピュアな感情を表現したいと思い、ミュージカル化にも挑戦しました。
「見返りを求めず、まっすぐに思いを伝える」という人魚姫の姿を、音楽や照明、踊りを駆使して体感できる舞台を実現することが私たちの目標となりました。
語る力を手放すという選択──人魚姫に託された沈黙の意味
フィエル――私は人魚姫に、そう名づけました。名前を持たない彼女に、語り手としての私の願いを込めて。フィエルは、魔女に“舌”を差し出して、人間になる薬を手に入れました。
それは、ただ声を失うということではありません。「語る力」を、自ら手放したということです。「語る」という字は、“言”に“舌”と書きます。つまり、語るとは、自分の舌で、自分の言葉で、自分の思いを話すこと。
その力を失ってまで、彼女は人間になろうとした。それは、王子に愛されたいという願いだけではなく、 「人間として生きたい」という、アンデルセン自身の叫びだったのではないかと私は思うのです。
舞台の上で、フィエルはセリフを言います。黙っていては観客に何も伝わりませんから。工夫として音響スタッフにエコーをかけてもらい、意味のある言葉ではなく、心の響きとしての声を届けました。
話せないけれど、気持ちは音楽と踊り、照明で表現しました。それは、私が「アンデルセンが舞台を作ったら、きっとこうする」と思いながら選んだ方法でした。
語り手として私は、こう感じました。語るとは、声を持つことではなく、舌を持つこと。そしてその舌で、自分の言葉を、自分の思いを、誰かに届けようとすること。
フィエルがそれを失ったとき、私は逆に、「語る」ということの重みを知ったのです。
『マッチ売りの少女』──灯りが生む希望と現実との葛藤
厳しい寒さの中でマッチを擦る少女が見た幻想は、単なる夢ではなく家族との思い出、温もりへの憧れが込められています。
彼女の幻想は、現実では届かない優しさや絆を象徴していますが、その一方で貧困や孤独への逃避でもあります。
語り芝居の中では、照明や音楽を使った演出で静かに“灯り”の持つ希望を届けつつ、どこか切ない現実も感じてもらえるよう心がけました。
現実超える“心の灯り”──語りが生むもう一つの世界
少女が灯りに包まれながら心の中に広げる幻想世界は、現実を超えて温かさや希望を感じられる空間です。“語り”のテンポや照明・音響の細やかな表現を工夫すると、観客の子どもたちは目を閉じ、その場にいるような臨場感を味わいます。
語り芝居だからこそ、言葉に頼らず“灯り”と“沈黙”で希望を伝えることができた、という舞台づくりの気づきを得ました。
舞台には、古びた木の椅子ひとつ。パーテーションを象徴的に配置し、照明と音楽だけで、少女の幻を描きました。焼きガチョウや銀の食器、暖炉の赤い火、大きなクリスマスツリー。
そして、おばあちゃんが天から迎えに来る場面では、光と神々しく優しい音楽を重ね、 天に導かれるシーンでは、星を散りばめる照明で表現しました。
語りの中で浮かび上がる“もうひとつの世界”は、 現実の苦しみを超えて、心の中に灯された希望です。
彼女の犠牲は、現実を生きる力を失っても、 誰にも気づかれない静かな強さとして、語りの中に残りました。
語り芝居だからこそ、言葉に頼らず、灯りと音と沈黙で語ることができたのです。
灯りとともに残る希望──語り終えた静寂
物語の語り終わりに、観客の子どもたちは静かな表情を見せていました。悲しみや喜びを声に出さず、灯りのような“ぬくもり”を心にしまっている様子が印象的でした。語り芝居は、悲しみや苦しみを語るだけでなく、小さな希望や温もりを子どもたちの中へ渡していく役割があると実感しました。
『すずの兵隊』ー沈黙の中の誇りと揺るがない意思
すずの兵隊は、片足しかなくても最後まで直立し、沈黙の中で自分の誇りを守り続けます。語り芝居では、動かない姿勢の意味や、無口な存在が持つ深い“心”の動きを表現することができました。
彼が犠牲にするものは愛や安全ですが、本当に伝えたいのは「自分らしさをいかに守るか」という生き方です。黙って立つことが語りになる瞬間を、子どもたちに感じてもらえるように演出しています。
動かない兵隊が語る“揺るがない心”
すずの兵隊は、片足しかなくても、まっすぐ立ち続けます。語りの中で、私は彼の動かない姿を、「動かないからこそ、心が動いている」と伝えました。
彼は、何も語らず、ただ沈黙の中に立ち続けます。その姿に、語り手として私は、“語らない語り”の力を感じました。
彼の犠牲は、自分を曲げないことによって、愛を失うこと。でも、最後まで誇りを持って立ち続ける姿に、 子どもたちは「かっこいい」と言いました。
それは、言葉ではなく、存在そのものが語った瞬間でした。
語り芝居だからこそ、沈黙と姿勢が語る物語を届けることができたのです。
語り手が見つけた“犠牲”の本質──選択が生む成長
語り芝居の中で気づいたことは、犠牲とは単なる悲しみや自己犠牲だけではありません。自分が信じるものや大切にしたい“心”のために、何かをあえて手放すことで新しい成長や誇りが生まれるのです。
子どもたちと物語を共有することで、それぞれが自分の選択を考えるきっかけになればと思います。
「犠牲」から考える三つの物語──異なる動機と選択の意味
人魚姫・マッチ売りの少女・すずの兵隊。これらの主人公たちが何のために“犠牲”を払ったのか、その動機には違いがあります。
愛されたいという願いや、家族への憧れ、誇りや理想を守る気持ち――それぞれの物語を並べてみると、選択する理由も手放すものも大きく違うことが分かります。
子どもたちに語り芝居として伝える際は、悲しみや孤独を美化しすぎず、真実の生き方について一緒に考える時間を大切にしています。
以下の表は、3つの物語を並べて見たときに浮かび上がる、主人公たちの選択とその意味を整理したものです。
読者の皆さん自身が「自分ならどうするか?」を考えるきっかけになれば嬉しいです。
アンデルセン童話に見る“犠牲”のかたち|3作品比較表
| 作品名 | 犠牲の内容 | 主人公の動機 | 結末 | 読者への問いかけ | 教育的・心理的な問題点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人魚姫 | 声・種族・家族・命 | 愛されたい/人間になりたい | 愛されず、泡となって消える | 自分を犠牲にしてまで、誰かに愛される必要はある? | 自己喪失・承認欲求の危うさ/沈黙の美化 |
| マッチ売りの少女 | 命・現実とのつながり | 寒さから逃れたい/愛された記憶に戻りたい | 幻想の中で死を迎える | 希望とは、現実から逃げることなのか? | 貧困・孤独の放置/死を美化する危険性 |
| すずの兵隊 | 愛・安全・生存 | 誇りを守る/まっすぐでいたい | 溶けて消えるが、最後まで姿勢を崩さない | 誇りを守ることは、命より大切なのか? | 感情表現の抑圧/自己犠牲の美化/報われない忠誠 |
表の読み方と、語り手としての深読みのすすめ
- 犠牲の内容 ただ「何を手放したか」だけでなく、その人が何を“奪われたか”にも目を向けてみてください。 それは、本人の意思ではなく、社会や環境が押しつけた犠牲かもしれません。
- 動機の違い 愛されたい、逃げたい、誇りを守りたい―― それぞれの主人公が、どんな心の動きでその選択をしたのかを感じてみましょう。 語り芝居では、その“動機”が語りの温度を決めます。
- 結末の共通点 3人とも報われません。 でもその中に、静かな誇りや希望が残っているように感じませんか? 語り手としては、その“残されたもの”をどう伝えるかが大切です。
- 問いかけの意図 この表は、読者の皆さんが「自分ならどうする?」と考えるきっかけになればと思って作りました。 語りは、問いを手渡すことでもあります。
- 教育的な問題点 悲しい物語ほど、美しく語りたくなります。 でも、死や孤独を美化しすぎないこと。 現実との距離を保ち、子どもたちが安心して物語に向き合えるように、語り手はいつも意識していたいですね。
まとめーアンデルセン童話で学ぶ「心で選ぶ生き方」
アンデルセン童話における犠牲は、誰かに強いられるだけのものではなく、自分自身で考え、選び取る“心の選択”です。人魚姫の挑戦、マッチ売りの少女の希望、すずの兵隊の誇り――どれも自分らしさを模索する姿に見えます。
大人も子どもも、物語を通じて自分の心と向き合い、選択する力を感じてほしいと思います。
語り芝居入門──一冊の絵本から始まる創造の世界
語り芝居は、個人でも少人数でも気軽に始められます。まずは好きな絵本を選び、声に出して読んでみましょう。その中に語りたい場面や言葉が自然と生まれてきます。照明や音楽、小道具の工夫も加えながら、自分らしい物語空間を創ってみることが大切です。
子どもの前で語るときは、“伝える”よりも“感じ合う”ことを意識しましょう。語り芝居は、物語を通じて語り手と観客が一緒に心を動かす貴重な時間です。台本は私が書いていますので、ご相談いただけるとうれしいです。
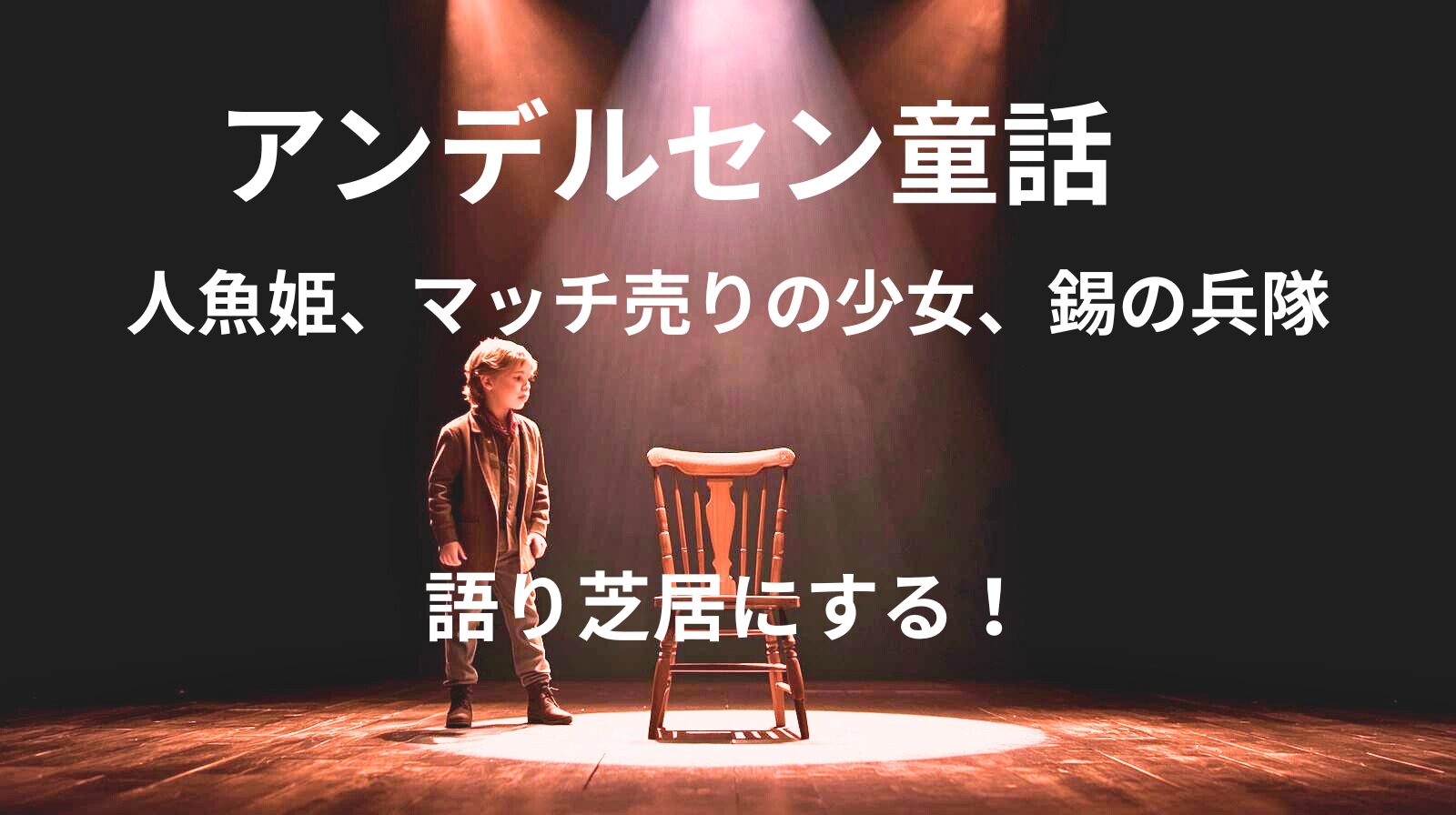
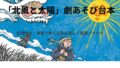
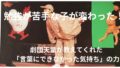
コメント