はじめに

「劇なんて難しそう…」「うちの子は人前が苦手だから無理かも」 そんな不安を抱える親御さんや先生にこそ、ぜひ一度『ブレーメンの音楽隊』劇を試してほしいと思います。 私自身、子ども達との家族劇、そして教室での実践を繰り返す中で、「できる」「できない」よりも、“みんなで一つの物語を作る感動体験”がどれほど子どもたちの心を勇気づけるかを心から実感しました。
子どもの「言葉にならない思い」をセリフや動き、そして仲間とのふれあいのなかで引き出す―― 本稿では、私や親子、教室で実際に経験した細かなエピソードを交えながら、劇の進め方やポイント、気持ちの動かし方まで、文字数を惜しまず詳しくお伝えします。
言葉にならない思いを引き出すには? 劇ならできる!
子ども達は言葉にならない思いを胸いっぱいに抱えています。語彙が少ない子どもは自の思いを伝えたいのに親がわかってくれない、どう表現していいかわからなくなると突然、乱暴な言葉を吐いたり、ドアや椅子や壁を蹴ったり、飲み物をひっくり返したり、幼児さんはお母さんに噛みついたりすることがあるのです。おとなはびっくりしまっておろおろしますよね。
幼児から中学生までの子どもなら一度や二度はこんな乱暴なことをやるのです。貴方のお子さんがおかしいのではありません。心配しないで!成長期の子ども達にふつうに起きることですから。
いらいらの原因は表現力不足
子どもが乱暴な口をきいたり、乱暴を働く原因は何かというと言いたいことがあるのにちゃんと伝わらない、親にわかってもらえないので感情が爆発してしまうからです。言葉にならない思いを伝える力が不足しているのです。つまり、表現力不足ということです。
そこでとても有効な方法をお知らせします。「お家で劇づくり」ということです。生身の親子関係は時にはギスギスして感情が爆発してしまうことはどの家庭でも起きています。
だからこそ、「お家で劇づくり」は、親子の間に安心と信頼の橋をかける素晴らしい方法なのです。劇づくりの中では、子どもは自分の気持ちを役になって表現することができます。
たとえば「怒っている子」や「悲しい子」など、実際の感情を少し距離を置いて演じることで、自分の中のモヤモヤを安全に外に出すことができるのです。
劇づくりの効果的なポイント
- 役になりきることで感情を客観視できる → 自分の気持ちを整理しやすくなります。
- 親も役を演じることで子どもの視点に立てる → 「そんなふうに感じていたんだね」と気づくきっかけになります。
- セリフを考えることで言葉の力が育つ → 表現力が自然と身につき、日常でも感情を言葉で伝えやすくなります。
このように、劇づくりは親子のコミュニケーションを深めるだけでなく、子どもの表現力や感情のコントロール力を育てるSEL(社会性と感情の学習)にもつながります。何より、親子で一緒に笑ったり、考えたり、演じたりする時間は、心の絆を強くしてくれます。
はじめの一歩として
「今日の気持ち劇場」と題して、1日の終わりに「うれしかったこと」「いやだったこと」を短い寸劇にしてみるのもおすすめです。家にあるぬいぐるみにセリフを言わせるのもOK。親子で役を交代して演じてみると、お互いの気持ちが深く伝わり思わぬ発見があるのでぜひやってみてください。

子どもが「親にわかってもらえる」と安心感を持つこと。それが、乱暴な言葉や行動の根っこを優しくほどいていく第一歩です。お家での劇づくりが、そんなやさしい土壌になるのです。
だからこそ、「お家で劇づくり」は、親子の間に安心と信頼の橋をかける素晴らしい方法なのです。劇づくりの中では、子どもは自分の気持ちを役になって表現することができます。
たとえば「怒っている子」や「悲しい子」など、実際の感情を少し距離を置いて演じることで、自分の中のモヤモヤを安全に外に出すことができるのです。
🎭 劇づくりの効果的なポイント
- 役になりきることで感情を客観視できる → 自分の気持ちを整理しやすくなります。
- 親も役を演じることで子どもの視点に立てる → 「そんなふうに感じていたんだね」と気づくきっかけになります。
- セリフを考えることで言葉の力が育つ → 表現力が自然と身につき、日常でも感情を言葉で伝えやすくなります。
このように、劇づくりは親子のコミュニケーションを深めるだけでなく、子どもの表現力や感情のコントロール力を育てるSEL(社会性と感情の学習)にもつながります。何より、親子で一緒に笑ったり、考えたり、演じたりする時間は、心の絆を強くしてくれます。
はじめの一歩として
「今日の気持ち劇場」と題して、1日の終わりに「うれしかったこと」「いやだったこと」を短い寸劇にしてみるのもおすすめです。ぬいぐるみを使ってもOK。親子で役を交代して演じると、互いの気持ちがより深く伝わります。
子どもが安心して「わかってもらえる」と感じること。それが、乱暴な言葉や行動の根っこを優しくほどいていく第一歩です。お家での劇づくりが、そんな優しい土壌になりますように。
実際に私の提案を取り入れてくださったご家庭では、親子関係が驚くほど良好になりました。お子さんは小学2年生、学校で友達関係がうまくいかなくて心が揺れ動く難しい時期でしたが、「お家で劇づくり」を通して、自分の気持ちを言葉や動きで表現する力が育ち、親御さんもその思いを受け止めやすくなったのです。
劇の中で交わされるセリフややりとりは、時に本音を映し出す鏡となり、親子が互いの気持ちに気づき、寄り添うきっかけになりました。感情の爆発が減り、代わりに「伝えたい」「わかってほしい」という気持ちが、穏やかな表現へと変わっていったのです。
このように、劇づくりは単なる遊びではなく、親子の心をつなぐ大切なコミュニケーションの場となります。難しい年頃だからこそ、言葉にならない思いを形にできる「劇」という方法が、親子の関係を深める力になるのです。
親子で劇づくりを始めてみる ブレーメンの音楽隊
あるご家庭での心温まるエピソードをご紹介します。ある日、お母さんが「誰でも知っている『ブレーメンの音楽隊』をやってみようか」と提案しました。「知ってるよ。次々に動物が出てくるんだよね」「おじいさんとおばあさんばっかり?」「老人ホームに行った?」「ブレーメンだよ!」

最初、男の子はお母さんの後ろに隠れるように立って、下を向いたまま。声をかけても、もじもじと小さくうなずくだけ。けれど、ロバの耳を頭につけてみると、少しだけ顔がほころびました。
「ロバさんは、おじいさんだから上手に歩けないのよね」と言うと、うん、と小さくうなづきゆっくりと足を引きずるように歩き始めました。「ほんとのロバじいさんみたい、うまいね!」と大袈裟なくらいに褒めると小さな声で「ヒヒーン」と鳴いてみせてくれました。お母さんが「上手!」と笑顔で拍手すると、彼の目がぱっと輝きました。
次は犬の役。四つん這いになって「ワン!」と吠えると、今度は自分から「お母さんもやって!」と声をかけました。お母さんが猫の耳をつけて「にゃーん」と鳴くと、二人は顔を見合わせて笑い、まるで本当の動物たちのようにじゃれ合い始めました。
ニワトリの役では、男の子が両腕を羽のように広げて「コケコッコー!」と元気いっぱいに叫び、部屋中に笑い声が響きました。最初の緊張はすっかり消え、親子の間には自然な会話と笑顔があふれていました。
劇の中で「仲間と力を合わせること」「自分の居場所を見つけること」といったテーマが、子どもの心にも響いたようでした。終わったあと、お母さんは「こんなに楽しそうな顔、久しぶりに見た」と話してくれました。
次はお父さんも妹も入れて劇をやってみようということになりました。
「ブレーメンの音楽隊」劇は“正しいセリフ”や“衣装”よりも、親子の小さな遊びから始めるのが一番の近道だと気づきました。
⭐️良い親子関係を作るのにとても効果があるのです。
配役どうする?家族会議のドラマ

配役の決め方にもドラマがあります。 「ロバやりたい、でも泥棒の役は絶対イヤ!」と主張する兄。 「猫しかやりたくない」と譲らない妹。 そこで長女が「じゃあジャンケンして、負けた人は“音楽係”でもいい?」とアイデアを出して家族みんな納得。
弟はじゃんけんに負けて「ぼく、ナレーターか…」と最初はがっかり気味。 しかし劇が進むにつれ、「みんなのセリフを紹介するの楽しいかも!次はリズム係やりたい!」と新たなやる気を見せはじめました。
母:「猫さんのセリフはどんな言葉にしたい?」 妹:「うまく歌えなくても、“ぼくはね、歌が好きだから負けない!”みたいにしたい!」 家族みんなで自分の気持ちをセリフに込める時間が、いつしか…夕食後のお楽しみのひとときになりました。
スマホ家族から会話家族になった!
劇づくりを家庭で始めてから、明らかに家族の空気が変わりました。以前は、食卓に並んでも誰も目を合わせず、スマホの画面ばかりを見ていた家族。それぞれが自分の世界に閉じこもり、会話は必要最低限。そんな日常が、劇の練習をきっかけに少しずつ変わっていったのです。
最初は照れくさそうだった子どもも、ロバの耳をつけて動いてみると、自然と笑顔がこぼれました。セリフをどう言うか、動きをどう工夫するか――親子で話し合う時間が生まれ、そこには「正解」ではなく「一緒に考える楽しさ」がありました。
劇の練習を通して、家族は互いの声に耳を傾けるようになり、ちょっとした気づきや感情を言葉にするようになりました。「このセリフ、なんだか悲しいね」「猫って、自由だけどさみしいのかも」――そんな言葉に、親は子どもの心の動きを感じ、子どもは親の共感に安心を覚えます。
気づけば、スマホを置いて向き合う時間が増え、家庭に会話が戻ってきました。劇の練習は、ただの遊びではなく、家族が心を通わせる「場」になったのです。
この変化は、特別な家庭だけのものではありません。ほんの少しの勇気と工夫で、どの家庭にも訪れる可能性があります。劇づくりは、親子の関係を深め、心の土台を育てる力を持っています。だからこそ、練習のあとの時間を大切にしてほしいのです。そこにこそ、教育の本質が宿っています。
練習中のハプニング~みんなで乗り越える
劇の練習は、必ずしも順調とは限りません。 「台本が覚えられない…」と泣きそうになった息子に、父親が「こういうとき、猫さんならどうする?」と役になりきる声かけ。
息子は「うーん、猫はどうせ失敗するって思われてるし…でも仲間がいるから平気って言うかも!」 そのセリフが実際に舞台に反映され、劇の流れも柔軟に変化。
家族みんなで「失敗しても劇の一部、アドリブで解決」を合言葉にしたことで、 緊張して固まりがちだった雰囲気に自然な笑いが生まれました。
練習後、母が「今日はどんな動きが一番楽しかった?」と質問すると、 「犬役で走るところ!猫の歌も好き!」とそれぞれがのびのび話してくれる時間が、演劇以上に心が近づく瞬間です。
練習の後の時間が大切
劇の練習が終わった後が実はとても大切。「さあ、もう劇は終わったのよ。宿題、さっさとしなさい」「お風呂、入りなさい」「散らかしたものはちゃんと片付けるのよ」と言いいたくなるのをぐっと我慢しましょう。
せっかく、家族みんなひとつになって良い親子関係ができているのをぶち壊してしまうことになってしまうので気をつけてくださいね。
私の劇団「天童」でも、稽古の後に子どもたち同士が役について自由に語り合う時間を大切にしています。セリフの言い回し、動きの工夫、役の気持ち――それぞれが自分なりの考えを持ち寄り、意見を交換することで、舞台の世界が少しずつ深まっていきます。
一見すると、ただのおしゃべりや雑談のように見えるかもしれません。しかし、この時間こそが、子どもたちの創造力や協調性、そして仲間意識を育てる貴重な場なのです。
自分の考えを言葉にし、相手の意見に耳を傾けることで、役への理解が深まり、気持ちがひとつになっていきます。
このような関係性の育ち方は、家庭での「家族劇」においてはさらに豊かな効果をもたらします。親子で一緒に役を演じ、練習を重ねる中で、互いの気持ちに気づき、思いやりが育まれていくのです。
劇の練習時間は、単なる準備ではなく、心を通わせる大切なプロセス。ぜひ、その時間を惜しまず、丁寧に積み重ねていただきたいと思います。これは、私自身が現場で何度も目にしてきた、確かな実体験です。
本番のリアル~ドキドキと涙と拍手
いよいよ発表会や家族劇の本番。 部屋を“ステージ”にして親戚や家族が観客役として拍手と応援を練習。
当日の朝は「おなかいたい…」とうずくまる娘。 母が「失敗しても誰も怒らないし、楽しかったらそれで100点だよ」と伝え、 「間違い探しゲームにしよう!」と舞台裏でジャケットを裏返しに着てわざと失敗するなど、緊張を和らげる工夫も。
劇が始まると、泥棒役の妹が“ヒエ~、ここは誰の家だ!”など大声アドリブで場を盛り上げ、 猫役の長男がセリフを忘れてしばらく黙り込んだ時、観客席から「がんばれ!」の声援が。 そこから彼は小声で「えっと、みんなで音楽隊作りたかったんだよ…」と言い直し、家族全員も思わず拍手。
カーテンコールには、父親がカスタネット、母がリコーダーで即興の伴奏を始め、 みんなで肩を組み「みんなで行こうブレーメン!」を大合唱。 本番後、涙ぐむ母に「やってよかったね!もう一回やろう!」と子どもたちが声を揃える、感動のシーンも。
リビングがステージ 客席はソファ
狭い家でもなんとかステージらしい雰囲気を作りましょう。リビングを片付けて俳優4人くらいがなんとか動ける空間を作ります。観客との距離は3メートルは欲しいですが、難しければ観客と2メートル、空けてください。客席はソファや小さな椅子を並べます。座布団を並べれば結構な人数が入れます.寄席みたいで楽しいものですよ。家族劇場ならではの親しみやすい感じが出れば全てOKです!
劇のフィナーレ~音楽と歌が心をつなぐ
フィナーレには家族みんなで即興の歌作り。 「どんな言葉が入れたい?」 「おなかすいたも入れていい?」 「泥棒追い出したら、やったね!も絶対!」 その場でメロディを口ずさみながら、楽器を持ち寄って合奏。 歌詞に「ひとりじゃないよ!」を入れたことで、兄弟喧嘩のあった前日まで笑い話として消化。
お互いの肩を抱き合いながら歌う時間は、「みんなで何かを創る」達成感。 終演後、「また次はどんな物語やろうか?」と家族会議がはじまりました。
カーテンコールは歌と振りでかっこよく!おすすめ

ミュージカル風な終わり方をするとかっこいいですね。カーテンコールの歌は即興でもいいですが、あらかじめ歌詞と曲を作り、歌稽古をしておくといいでしょう。家族みんなで詩を作り、曲はお気にりの曲をアレンジした感じでもいいと思います。役者のソロがあるのがふつうです。曲の終わりは出演者全員のコーラスで締めくくります。ミュージカル俳優になったつもりで良い気分で舞台を終わるようにしましょう!
劇のあとの余韻~親子ふりかえりの時間
劇が終わったあと、親子で語り合うひととき。 「劇で一番うれしかったことは?」 「猫役で困ったときに、兄がセリフを助けてくれてうれしかった」 「ロバ役で走ったらみんな笑ってくれた!」 「劇中の“ありがとう”“ごめんね”が本当の気持ちみたいで、普段より素直に言えた気がする」
普段は照れて言えない感情も、劇の“セリフ”や“動き”を通じて自然に言葉になる。 父親は「ふりかえりノート」を作り、子どもたちが劇の感想を書いたり絵に描いたりして振り返り。 母親は「劇を通して、どんな気持ちも全部大事って伝えられるようになった」と感じています。
親子兄弟、心の距離が縮まった
家族劇の後はなんとなく親子、兄弟の間にあった目に見えない壁が消えてしまい、お互いに懐かしい感じがしてくるのです。お互いの名前を呼び合う時の声が、ロバの声だったり雄鶏が泥棒を襲う時の声だったりで思わず顔を合わせて笑ってしまうことがあります。家族劇にはこんなすてきな効果があるのです。お祭りの後に御神輿を担いだ仲間がぐっと親しくなる、あんな感じです。
失敗したときの対処法~現場からのアドバイス
家族劇での“失敗”は、親子の絆を深めるチャンスだと思ってください。家族劇の本番中、子どもがセリフを忘れてしまったり、動きが止まってしまったりすることはよくあります。ある日、劇の途中で男の子が急に泣き出してしまいました。緊張と恥ずかしさが重なったようでした。親は「大丈夫、やり直そう」と声をかけるのをぐっとこらえ、子どもの隣にそっと寄り添い、男の子のセリフが出るような言葉を出して待ちましょう。
それでもセリフが出てこない場合は、「〇〇に行くんだね?」とセリフを思い出させるように話しかけます。「〇〇に行く」のセリフを聞いたとたん、「そうだ、これがぼくのセリフだ!」と思い出しパッと明るい顔になって自分のセリフを言ってくれます。助け舟の出し方を覚えておくといいですね。
家族劇は、親子が同じ舞台に立ち、同じ物語を紡ぐ貴重な時間です。だからこそ、失敗も“物語の一部”として受け止めることで、親子の関係がより深く、あたたかくなっていきます。
失敗したときこそ、親のまなざしが問われます。温かく、信じて、待つ――それが、子どもにとって何よりの支えになるのです。
SEL的効果~感情と言葉と協力が育つ時間
『ブレーメンの音楽隊』劇は、ただセリフを覚えるだけでなく、自分の感情を言葉にする練習 仲間と協力し解決・分担する体験 失敗も笑顔で受け入れる安心感 親子でひとつの物語を創る達成感 を育てる素晴らしい教材です。
難しい教育理論よりも、「楽しかった!」「みんなが一緒で心強かった!」 その気持ちを楽しみながら繰り返すうちに、自然と心と社会性が伸びていくことを実感できます。
家族っていいね、またやりたいと思えれば最高!
「ああ、楽しかった」「あの失敗、笑っちゃったね」「もう一回やりたいね」「お父さん、笑わせるの上手だ、知らなかったよ」「お母さんの泥棒役、こわかったね、いつも怒っているからうまくいくんだよ」「ブレーメンに行かなくてよかったね」
親は子どものことがわかり、子どもは親を見直し、家族っていいもんだと思えれば家族劇は大成功!上手に演じることより家族の誰もが自分の感情を出し合えれば最高だと思ってください。
まとめ~体験そのものが最高の教育
劇づくりは、「できる・できない」を問うものではありません。うまく演じられなくても、セリフを忘れても、笑ってやり直せばいい。大切なのは、“みんなで作る”“一緒に失敗も笑う”という体験そのものです。そこにこそ、子どもたちの心が育つ土壌があります。
物語の力は偉大です。ロバや猫になりきることで、子どもは自分とは違う気持ちに触れ、親はその姿を通して子どもの内面に気づきます。親子が同じ物語を共有し、同じ空気を吸いながら笑い合う――そんな時間が、家庭を非日常の楽しい場所へと変えてくれるのです。
どんなに小さな劇でも、「やってみたい!」という気持ちがあれば、それで十分です。紙の耳をつけて、ぬいぐるみを使って、リビングが舞台になります。そこから始まるのは、ただの遊びではなく、親子の心が通い合う“生きた時間”です。
劇団天童の現場でも、子どもたちは失敗を重ねながら、仲間と支え合い、役の気持ちを語り合い、少しずつ自分の言葉を見つけていきます。家庭劇でも同じです。親が温かい目で見守り、子どもが安心して表現できる場をつくることで、心の根っこが育っていきます。
どうか、劇づくりの時間を「特別なこと」と思わず、日常の中に取り入れてみてください。あなたの家庭が、ちょっとドラマチックに、そして何より、あたたかく変わっていくはずです。
おまけ 「ブレーメンの音楽隊」物語のあらすじ 絵で楽しんでください





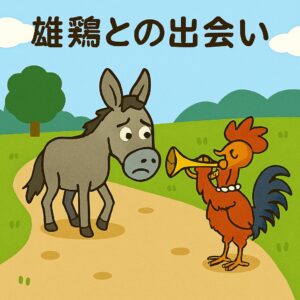

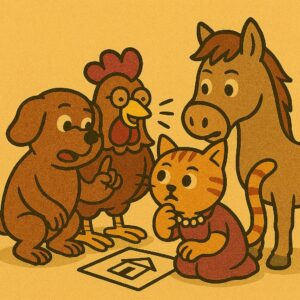
作戦会議
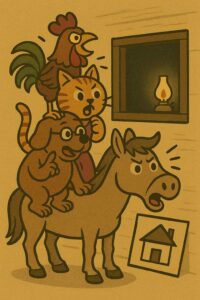
泥棒がいるぞ!


やっつけろ!

ここで暮らそう!

素晴らしい音楽を聞いてください!
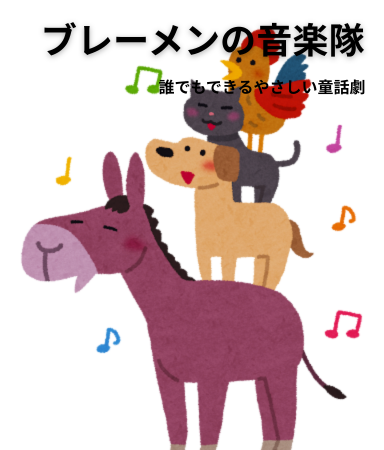


コメント